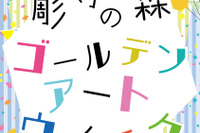なぜ今、小学校からプログラミングを学ぶのか。プログラミングでどんなことができるのか。今さら人に聞きにくい「そもそも」の疑問を、やさしい言葉とポップなイラストでわかりやすく教えてくれる素敵な絵本が登場した。未就学児から大人まで、プログラミングの入り口に立つすべての人に読んでもらいたい「こどものためのプログラミング」シリーズ(保育社)だ。
この絵本を翻訳したのは、若き天才プログラマー、矢倉大夢(やくらひろむ)さん。矢倉さんは1996年生まれの22歳。灘中学校・高等学校でパソコン部に所属し、「未踏 IT人材発掘・育成プロジェクト(*)」での採択や国際情報オリンピック代表候補に2回選出されるなど、国内外で数々の受賞歴があり、現在は筑波大学大学院で音声・音楽情報処理を研究し、国立研究開発法人産業技術総合研究所にも所属。さらに、企業のグローバルリーダー育成を行う企業、チームボックスのCTO(最高技術責任者)を務め、研究成果をリアルな社会でも実践している。*独立行政法人情報処理推進機構が、ITを使ってイノベーションを作り出せるアイデアや技術をもった若い人材を発掘・育成する未踏人材発掘育成事業のこと
子どものプログラミング教育は「そもそも何のために必要か?」。今さら聞きにくい基本を矢倉さんにうかがった。
プログラミング学習と英語学習は似ている
--なぜこの本を翻訳することになったのですか。
出版社の方が、対象年齢よりも少しだけ年上の、子どもたちのお兄さん的な若いプログラマーに翻訳してほしいと思っていたそうで、お声がけくださいました。
この絵本はアメリカでシリーズ化されていて、今回僕は「くらしの中のプログラミング」「アイデアを形にする、シェアする」「役立つアプリをつくってみよう!」「ゲームとアニメーション」というテーマの4冊を翻訳しました。実際に読んでみると、あぁ、これは僕自身がもっと早いうちに出会いたかった!と感じました。
 自身がもっと早いうちに出会いたかった!という絵本「こどものためのプログラミング」を翻訳した矢倉さん
自身がもっと早いうちに出会いたかった!という絵本「こどものためのプログラミング」を翻訳した矢倉さんコンピューターって、普段はその存在を意識することはないけれど、僕らの日常生活や、いつも遊んでいるゲームにも深く関わっていて社会の根幹には欠かせないものになっています。そうした背景を子どもでも理解しやすいように、親しみやすい事例をつかって説明してくれているんです。
--保護者や先生方が小学生のころにはそもそもプログラミングなんて授業には存在しなかったので、「プログラミングってどんな子にも必要なの?」「どんなものか知っておいたほうがいいの?」と、まだたくさんの大人がそこで立ち止まっている気もします。
プログラミングは知っておいたほうがいいというよりも、知らないとまずいです(笑)。プログラミングを仕事にしていかなくても、使えば何ができるかというのを知っておくことはとても重要だと思います
--プログラミングをするのはプログラマーになるためだけではないということですね。
そうです。通訳になろうと思っていなくても英語を学ぶのと同じように、プログラマーになろうと思っていなくてもプログラミングを勉強するということです。
でも、コード(命令)を並べて、手続きを書いて完成ということだけがプログラミングの世界だと教わると、とても退屈なものに思えてしまうでしょう。プログラミングはコンピューターの中で完結するものではなく、身の周りのいろいろなものとつながって、環境がどんどん変えられるんだという実感をもってほしいです。
--英語の勉強と似ていますね。
そうだと思います。文法のルールや単語ばかり詰め込まれても、全然面白くないですよね?英語ができるようになればどんな未来が実現するのか。英語ができるようになった“先”が少しでも見えたら、未来の自分の可能性が広がると思えるようにもなり、英語の文法や単語を覚えることも楽しくやれるはずです。
だからこそ、プログラミングでどんなことができるようになるかを教わらず、ただルールどおり“やらされている”だけでは、逆にプログラミング嫌いが増えてしまうのではないかと心配です。
子どもが実際にパソコンをさわる前にこの絵本を読んで、プログラミングでどんなことができるのか、世界はどう広がるかという前提知識があれば、プログラミングを実際に学ぶ際のハードルがぐんと下がるのではないでしょうか。
身近にあるプログラミングを知る
--絵本にはゲームや車、信号、家電製品、ロボット、バーコードなど、たくさんの事例が出ていますが、そのほかにも身近でプログラミングが使われている例はありますか。
たとえば音楽やアートなども、今はプログラミングを組み合わせて作品が作られています。アーティストやミュージシャンにもプログラミングを学んでいる人は非常に多いです。
--プログラミングを「早いうちから慣れさせたほうがいい」と考える親御さんも多く、子どもに習わせたい習い事ランキングでは英会話と並んでトップという調査結果もあります。矢倉さんはいつから始めたのですか。
僕は中学に入ってからプログラミングを始めたので、まだキャリアとしては10年くらいです
--意外と遅いスタートだったんですね。
最近の小学生と比べたら遅めのスタートだったかもしれません。入部した理由も古びた部室の雰囲気に惹かれたからで、パソコン部に入ってから、そこではプログラミングをしないといけないというのを初めて知ったというレベルでした(笑)。パソコン自体は小学校にも家にもあったのですが、プログラミングは全然知りませんでした。
--早くから始めたほうがいいのでしょうか。
必ずしも早いほうがいいともいえないです。小学校1、2年生だと、プログラミングの条件分岐といった概念がそもそも脳の構造的にまだ馴染まないという研究結果もあります。
--小学校のお子さんたちが始めるとしたら、どんなことに気をつければいいですか。
やっていて“楽しい!”と思うことが一番大事です。まだ小さいころは目に見えてわかりやすいこと、そして何よりも楽しさを優先したほうがいいと思います。スクラッチとかロボットなんかだと、わかりやすくていいですね。スクラッチだと無料のサイトもあるし、最近ではいい本もたくさん出ていて制作の流れもわかりやすいので、親子で一緒にやってみてもいいと思います。
 「プログラミングは、やっていて“楽しい!”と思うことが一番大事」
「プログラミングは、やっていて“楽しい!”と思うことが一番大事」先生の準備で大切なこと
--プログラミングを教える小学校の先生は、どんなことを準備すればいいと思いますか。
授業の一番はじめに、こういう絵本の話を子どもたちに読み聞かせて、見せてあげてほしいなと思います。最初からスクラッチでゲームをつくります、といっていきなり始めてしまうと、子どもたちは「プログラミングってゲームをつくるってことなのね」と思ってしまうと思うので。
先生方が今の環境でプログラミングを教えるというのは確かに大変だと思いますが、だからこそ子どもたちに、具体的に何をどう教えるかという中身に入る前に、プログラミングがあるとこんなにできることがあるんだという「気持ち」だけは実感としてもっていてもらいたいです。そのためには、先生自身が簡単なもの、たとえば子ども向けのゲームでもいいし、エクセルのマクロのようなものでもいいので、何かひとつ“自分でつくってみる”という体験をしてほしいです。
--プログラミングの授業で全員に同じものをつくらせようとすると、それは相変わらず“1つの正解を求める”という古い教育ではないかと懸念する声もあります。
僕は最初のステップとしては、みんなで同じものをつくることは悪くはないと思います。たとえば音楽の授業って、みんなで同じ歌を歌いますけど、その中でひとりひとりが自分の感性で音楽に触れて、音感を身に付けていきますよね。
ただそこから、もっと自分なりに良いものにしたい、自由につくりたいと思ったときには、まわりに詳しい人がいるかどうかが重要になってくると思います。
--矢倉さんにとって、部活の仲間の存在が大きかったのでしょうか?
そうですね。自分でつくりたいなと思っても、エラーが出たり、自分ではよくわからないところでうまく動かないことがたくさん起こるので、そのときに聞ける人がそばにいたのは大きかったです。
プログラミングで変わる未来
--ところで矢倉さんは、どんな小学生でしたか。
プログラミングとはまったく関係のないことをたくさんやっていました。小学校に入る前から、親がよくいろいろな体験教室に連れて行ってくれて、電子工作や農業体験、それに能楽の体験なんかにも結構ハマりました。落語にも興味があって、親に頼んで寄席に連れて行ってもらったこともありました。
電子工作は今やっているプログラミングに直接関わるものですが、それ以外にもいろいろなことにチャレンジしてみたい、知りたいという好奇心が人一倍強いのは、そういった幼少期の多様な体験が足場になっている気がします。
--親や先生にとって、プログラミングに対する一番大切な心構えを教えてください。
プログラミングでは、最初からすべて正しくつくることができるということはなく、必ずといっていいほどどこかで間違えるものです。誤りを見つけて修正することをデバッグと呼ぶのですが、プログラミングはデバッグを何度も繰り返し、試行錯誤を重ねてつくっていきます。このデバッグの思考を一番大切にしてほしいと思います。たとえばロボットが真っ直ぐ進まずに逆走したり、止まらずに落ちてしまったり、そういう想定外のハプニングをみんなで面白がれる雰囲気になってほしいなと思います。どんなに間違えたって、最悪電源を抜いちゃえば止まるというのがコンピューターのいいところなので(笑)。プログラミング教育を通じて、失敗しても、試行錯誤してまた作り直せばいいんだ、答えはひとつだけじゃないんだという思考になっていくといいですね。
--プログラミング教育で、未来はどんなふうに変わっていくと思いますか。
先生の役割は変わっていくでしょう。これまでは知識のインプットがおもな役割でしたが、今後はテクノロジーが生徒ひとりひとりの理解度からモチベーションまで細かく把握していけるようになるので、むしろこれからは生徒たちに伴走し、共に学び、より深い学びのためにファシリテートしていく方向になっていくだろうと思います。
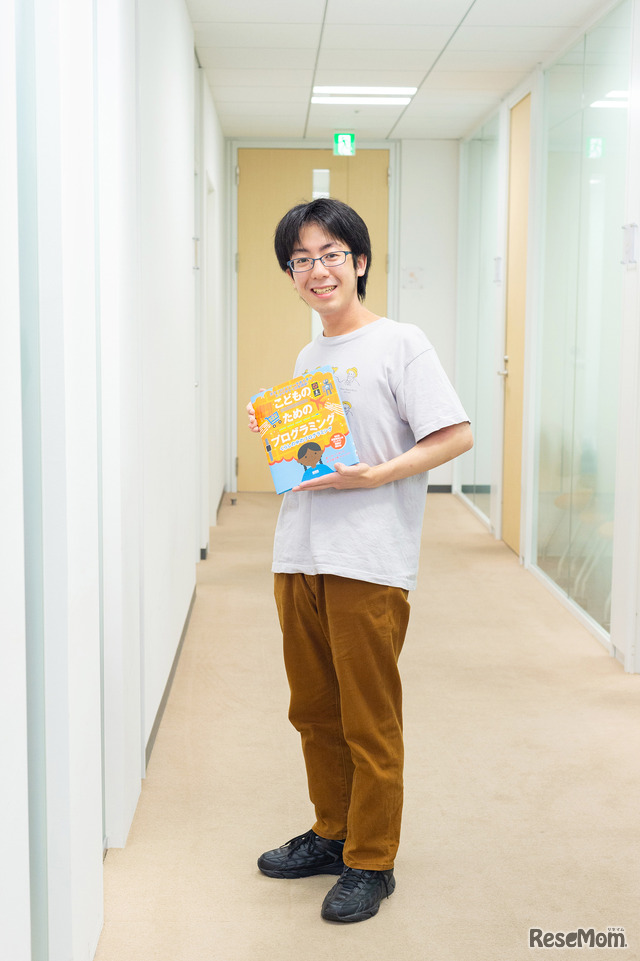 「先生の役割は、生徒たちに伴走し、共に学び、より深い学びのためにファシリテートしていく方向になっていく」
「先生の役割は、生徒たちに伴走し、共に学び、より深い学びのためにファシリテートしていく方向になっていく」社会全体では、IT専門職というものの規模が小さくなり、それぞれの業界の中でITの得意な人が活躍していく世界になるのではないかなと思っています。どんな業界、職種であれ、ITやプログラミングの知識がないと仕事がしにくくなっていくでしょう。だからこそ、テクノロジーで何ができるのかを“肌感覚”で、子どものころから身に付けておくことがとても重要です。
この絵本シリーズを気軽に手にとって読んでもらい、そんな“肌感覚”が楽しく身に付くようお手伝いができれば嬉しいです。
--ありがとうございました。
親や教師自身が体験したことのないプログラミングの授業。なぜプログラミングがこれからの子どもたちに必要なのか、“本質”のところをわかりやすく教えてもらえたインタビューだった。
物腰は優しく、柔らかい雰囲気の矢倉さんの紡ぐ言葉は、美しいプログラミングコードのように無駄なく不足もなくわかりやすい。この絵本の翻訳をきっかけに、教育の分野への思いが強まったという矢倉さん。その稀少な才能と人柄を掛け合わせた活躍を、今後も一層期待したい。
※リセマムでは、矢倉大夢さんが翻訳した絵本、保育社の「こどものためのプログラミング」シリーズ4冊をセットで抽選のうえ1名さまにプレゼントする。ご応募は2019年9月23日(月)まで。