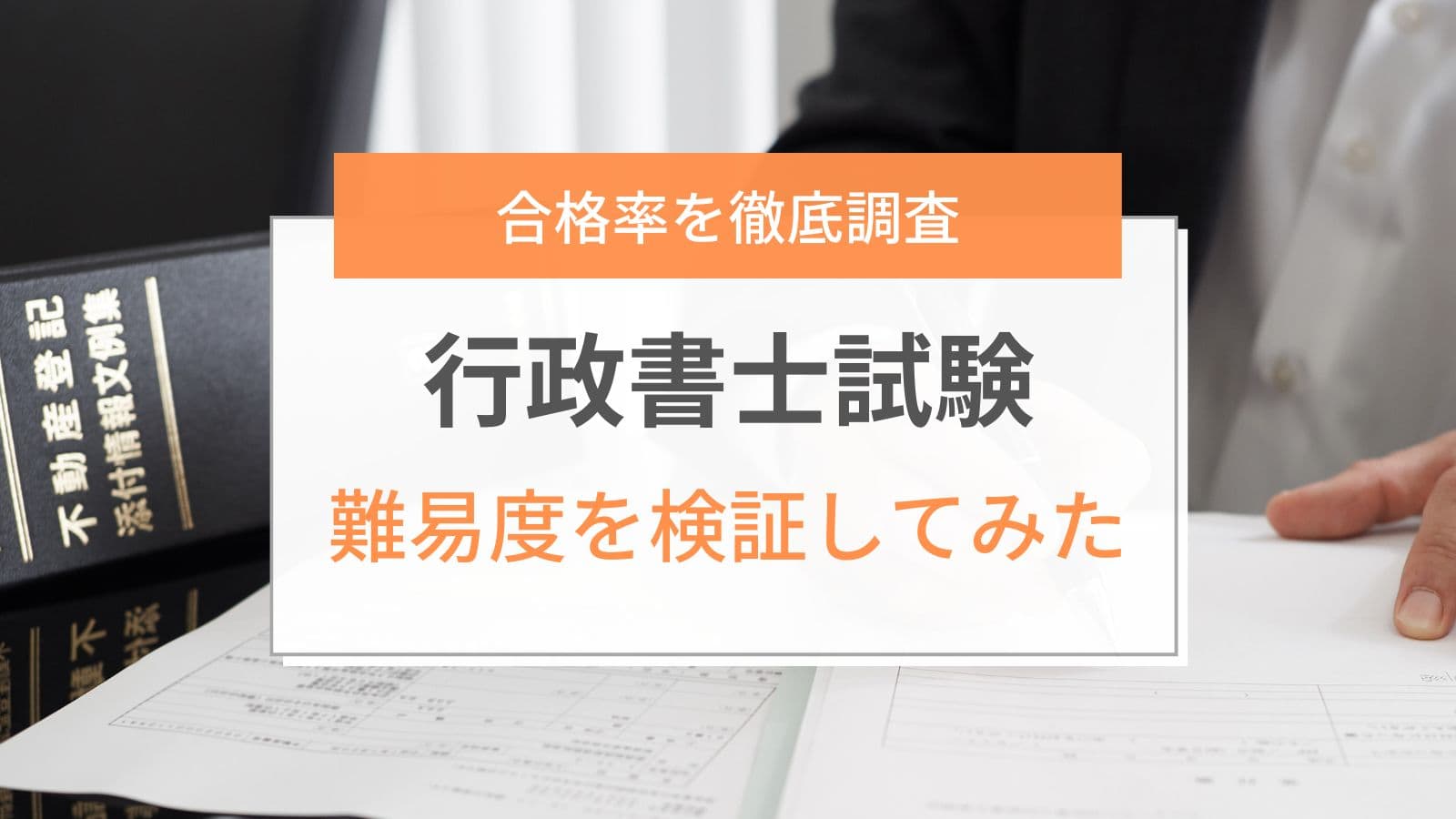行政書士の毎年の合格率は約10%で難関資格といわれています。
予備校に行くのが当たり前で、独学で合格するのは難しいです。
試験に合格するためには、1月から始めたとして、半年以上の勉強期間は必要だと考えられます。資格取得を検討している方は早めに学習をスタートさせましょう。
学習期間が長く難易度が高い行政書士ですが、今回の記事では以下のような内容について調査を実施しました。
今回は、上記の内容をそれぞれ詳しく解説していきます。(5分ほどでサックリ理解できるようまとめました。)
そもそも行政書士とは?どんな仕事内容?
日本行政書士会連合会によると、行政書士とは以下のように定義されています。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明および契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。
引用:日本行政書士会連合会
最新!行政書士試験の日程を紹介
行政書士試験の日程については、例年7月に発表されます。
スケジュールを把握しておくことで、目標とする受験日や学習計画を立てやすくなります。
| 申込期間(郵送) | 令和7年7月22日(火)~8月18日(月)消印有効 |
| 申込期間(Web) | 令和7年7月22日(火)午前9時~8月25日(月)午後5時 |
| 試験日 | 令和7年11月9日(日)午後1時~午後4時 |
| 合格発表 | 令和8年1月28日(水) |
行政書士の試験範囲や試験科目、合格基準は?
行政書士の試験科目は「行政書士の業務に関し必要な法令等」と「行政書士の業務に関連する一般知識等」にわけられます。
「行政書士の業務に関し必要な法令等」は244点満点で、「行政書士の業務に関連する一般知識等」は56点満点です。
「行政書士の業務に関し必要な法令等」では以下の科目が出題されます。(問題数は全部で60問)
- 憲法
- 行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法が中心)
- 民法
- 商法・会社法
- 基礎法学
また「行政書士の業務に関連する一般知識等」は以下の通りです。(問題数は14問)
- 政治
- 経済
- 社会
- 情報通信
- 個人情報保護
- 文章理解
試験の合格基準は以下のように定義されています。
引用:一般財団法人行政書士試験研究センター
- 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、122点以上である者
- 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、24点以上である者
- 試験全体の得点が、180点以上である者
行政書士が注目されている理由
行政書士に注目が集まっている理由は以下の通りです。
- 将来独立や開業ができる
- 法律の知識が身につく
将来独立や開業ができる
行政書士は独立や開業ができます。行政書士の資格は、行政と書類や契約書などの文章作成業務ができます。
この業務は独占業務のため、ほかの資格では対応ができず安定した収入につながるからです。具体的には県や市に対して企業からの書類作成依頼や、国との公共事業に対しての書類作成などが該当します。
資格の名前が似ている司法書士は、これらの業務を担当できないため、一定の顧客を持てば独立や開業も可能です。
法律の知識が身につく
行政書士は一般的に法学関連の資格とみなされています。理由は、行政とのやりとりに必要な法律や規則を理解しなければならないからです。
行政法や商法など企業と官公庁との文章のやり取りでは、2つの法律を理解しなければなりません。そのため行政書士の資格を取得するときに、法律関連の知識が身につきます。
行政書士が難しいといわれている理由
行政書士が難しいといわれる理由は以下の通りです。
- 法学資格では簡単な部類のため、受験者が対策を怠る
- 出題形式が5者択一式・多肢選択式・記述式で正解する可能性が低い
- 足切りラインが設けられている
行政書士は司法書士や弁護士に比べて簡単な資格とされています。しかし行政書士の合格率は非常に低く、10%台が続いています。
また試験の出題形式が2択ではなく、5択で順番に選択する形式のため正解するのが難しいです。
行政書士の足切りラインは以下の通りです。
- 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50パーセント以上
- 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上
合格するためには、2つの条件を満たさなければなりません。
行政書士の合格率から見る難易度
行政書士の合格率は以下の通りです。
| 年度 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 13.98% | 46,991 | 6,571 |
| 令和4年度 | 12.13% | 47,850 | 5,802 |
| 令和3年度 | 11.18% | 47,870 | 5,353 |
| 令和2年度 | 10.7 % | 41,681 | 4,470 |
| 令和元年度 | 11.5 % | 39,821 | 4,571 |
| 平成30年度 | 12.7 % | 39,105 | 4,968 |
| 平成29年度 | 15.7 % | 40,449 | 6,360 |
| 平成28年度 | 9.95 % | 41,053 | 4,084 |
| 平成27年度 | 13.12 % | 44,366 | 5,820 |
| 平成26年度 | 8.27 % | 48,869 | 4,043 |
| 平成25年度 | 10.10 % | 55,436 | 5,597 |
| 平成24年度 | 9.19 % | 59,948 | 5,508 |
行政書士の合格率が低い理由は、
- 受験者の対策不足
- 足切りラインがそもそも高い
- 受験者数で合格者数を調整している
が挙げられます。
とくに合格者の数は毎年相対評価で数を決めています。択一式問題の得点率で記述式の採点をきびしくしたり、優しくしたりします。
また永田町司法書士事務所が発表した内容を参照すると、行政書士におすすめの通信講座を利用することで、令和4年度の合格率は56.17%と、全国平均(12.13%)の4.63倍を達成し、加えて合格者数206名中196名は一発合格したとのレポートも。
行政書士の勉強時間から見る難易度
行政書士に合格するためには最低でも1,000時間必要とされています。独学者や法学初心者は、必ず1,000時間確保できるようにしましょう。
法学部出身や法律関連の業務を経験された方は、1,000時間未満で合格できる人もいます。
しかし、試験対策は半年以上の期間が必要です。
学習経験者でも、余裕を持って対策ができるように早めの対策をしましょう。
具体的には、2027年の試験合格を目指す場合、1年であれば2026年の11月、半年であれば2027年の1月から6月までの間に学習を始めます。
試験のスケジュールも確認しながら、十分な勉強時間を確保できるように計画を立ててください。
行政書士の年齢別合格率から見る難易度
行政書士の年齢別合格率は以下の通りです。
| 年代 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10歳代 | 9.10% | 10.10% | 8.20% | 8.9% | 7.5% |
| 20歳代 | 18.30% | 16.40% | 12.80% | 15.4% | 13.5% |
| 30歳代 | 19.00% | 16.10% | 13.50% | 13.7% | 14.4% |
| 40歳代 | 15.50% | 12.40% | 11.50% | 9.8% | 10.9% |
| 50歳代 | 12.50% | 9.50% | 10.10% | 7.3% | 8.9% |
合格率を年代別にわけると、幅広い受験者が合格しているのがわかります。
弁護士や公認会計士のように、学生だけで8割の合格者を占めることはなく、社会人も多く合格しています。
とくに30代前後の合格率が最も高く、社会人でも管理職手前の年齢の方が多いです。
学生のときに合格する方も一定数いますが、社会人ほど多くなく、むしろ少数です。
ほかの資格と比較した場合の難易度はどれくらい?
行政書士と難易度が似ている資格は以下の通りです。
| 資格名 | 偏差値 | 平均合格率(直近10年分) |
|---|---|---|
| 行政書士 | 62 | 10% |
| 簿記1級 | 67 | 10% |
| 社労士 | 65 | 4% |
| 気象予報士 | 64 | 5% |
| 中小企業診断士 | 67 | 5% |
行政書士の資格は難関と言われている気象予報士や中小企業診断士と同等の難易度です。
合格率が低く、受験者も一度の受験で合格できる人が少ないのが特徴。
行政書士よりも簡単な資格として挙げられるのは、
- 簿記2級(偏差値58)
- FP(ファイナンシャル・プランナー)[AFP/CFP] CFP(偏差値58)
- 管理栄養士(偏差値62)
です。