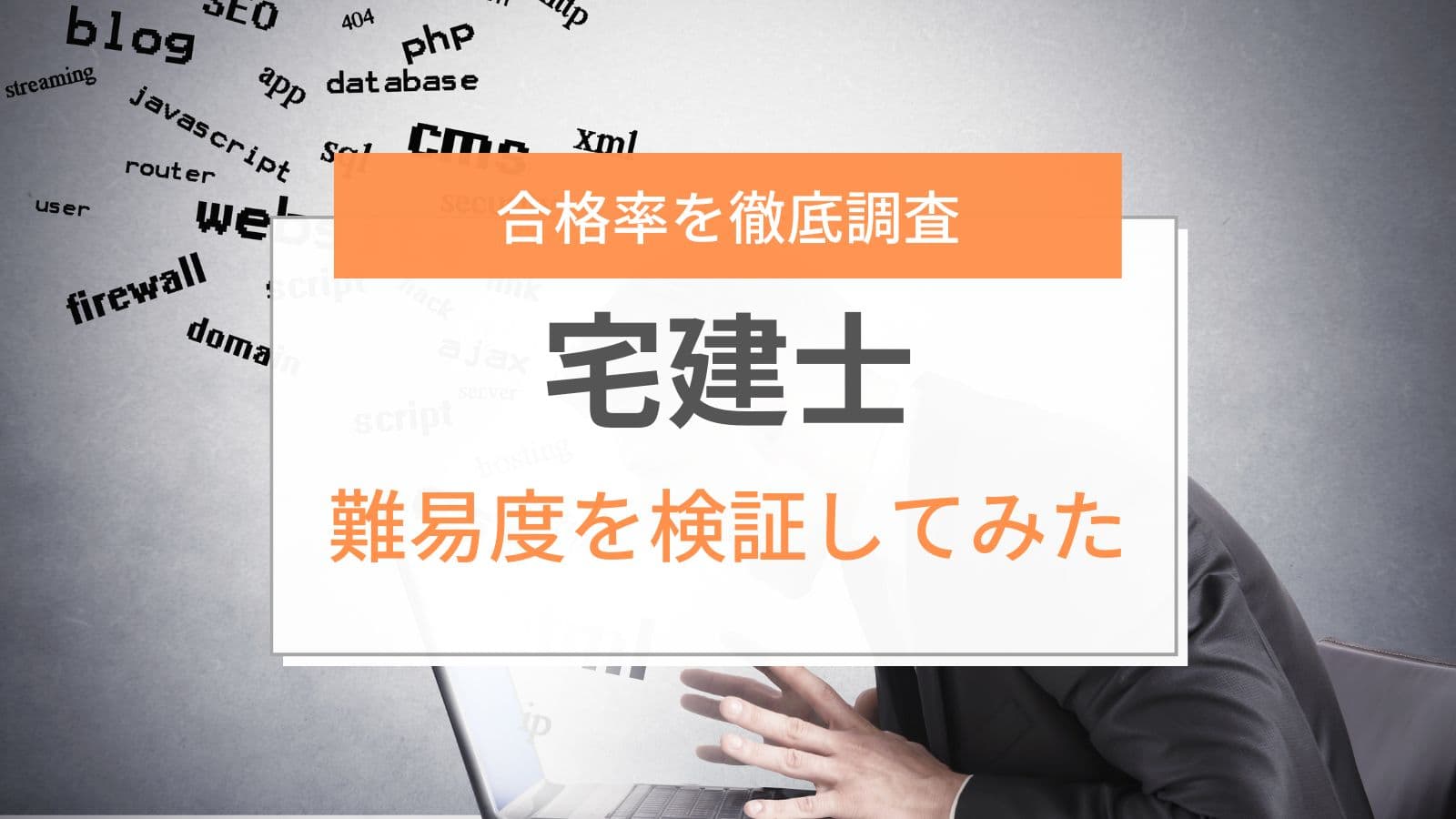宅建士(宅地建物取引士)はとくに不動産業界で必要とされる専門性の高い職種です。宅建士(宅地建物取引士)を目指すには宅建試験を受ける必要がありますが、この試験は合格率17%前後と難易度がとても高いことが分かりました。
そこで、今回は以下のような内容について調査を実施しました。
【当ページをざっくりまとめると…】
・宅建士は17%前後の合格率で難易度は高め
・4科目のうち出題は全50問、勉強時間は300時間程度確保がおすすめ
・不動産関連の資格の中では最初に取得されやすい資格
・一般的なほかの資格の中では合格率が低く難易度が高いとされる
・不動産業界で働いている社会人の方が実務経験から理解しやすく合格に有利
宅建に合格するためには、2026年2月現在から始めたとして、300時間程度は確保しておく必要があると言われています。難易度も高いので、宅建士の資格取得を検討している方は早めに対策をしましょう。
今回は、上記の内容をそれぞれ詳しく解説していきます。(5分ほどでサックリ理解できるようまとめました。)
宅建士(宅地建物取引士)の合格率から見る難易度
| 年度 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 平成26年度 | 192,029 | 33,670 | 17.5 |
| 平成27年度 | 194,926 | 30,028 | 15.4 |
| 平成28年度 | 198,463 | 30,589 | 15.4 |
| 平成29年度 | 209,354 | 32,644 | 15.6 |
| 平成30年度 | 213,993 | 33,360 | 15.6 |
| 令和元年度 | 220,797 | 37,481 | 17.0 |
| 令和2年度(10月試験) | 168,989 | 29,728 | 17.6 |
| 令和2年度(12月試験) | 35,261 | 4,610 | 13.1 |
| 令和3年度(10月試験) | 209,749 | 37,579 | 17.9 |
| 令和3年度(12月試験) | 24,965 | 3,892 | 15.6 |
| 令和4年度 | 226,048 | 38,525 | 17.0 |
| 令和5年度 | 233,276 | 40,025 | 17.2 |
直近10年の合格率は15.0~18.0%で推移していることが分かります。また、新型コロナウイルス感染症対策により、直近2年は試験を年2回に分けて実施し、10月の試験よりも12月の試験の方が合格率が数%下がっています。
試験日や会場は主催側が指定します。そのため12月試験になった場合、合格率が10月よりも下がってしまう、つまり難易度が上がってしまうかもしれません。
ここ数年は17%に推移しているので、難易度が易化していくことを期待するでしょう。しかし全体的に合格率は20%を超えておらず、難易度は高いです。
しっかりと準備をしてから試験に挑むこと、そして一発合格は難しいことを予め理解したうえで試験勉強を進めてみてください。
宅建士(宅地建物取引士)の勉強時間から見る難易度
| 科目 | 出題数 |
|---|---|
| 宅建業法 | 20問 |
| 民法など | 14問 |
| 法令上の制限 | 8問 |
| 税・その他 | 8問 |
宅建の試験で出題される主な科目は上記の4種類です。それぞれ出題範囲がかなり膨大で、法律を理解するだけでも時間がかかってしまいます。
推奨する勉強時間は200~300時間で、1日1時間だけ勉強をすると決めていても、約1年近くかかってしまいます。
不動産関係の知識が一切なくゼロからのスタートであれば、勉強時間は休日を中心に確保しておくこと、試験までにゆとりを持っておくことがおすすめです。
宅建士(宅地建物取引士)の受験回数から見る難易度
宅建士の試験に合格するまでの受験回数は平均2回です。合格率が20%以下と低いため、一発合格が難しいことは推察できますね。しかし多くは過去問から再度出題されるため、一度対策が分かれば試験に合格するコツもつかみやすいです。
宅建士に合格した方の、受験回数をまとめると以下の通りです。
・1回の受験で合格:約40%
・2回の受験で合格:約30%
・3回の受験で合格:約10%
回数の割合を見ると、一発合格している方が一番多い結果でした。
合格率は低いですが、効率よく学習を進めることで試験合格も目指せるでしょう。
宅建士(宅地建物取引士)の学歴から見る難易度
宅建士の資格を取得する際に受験要件はありません。そのため、何歳であってもどんな学歴であっても受験することは可能です。
受験時に最終学歴を提出していないため、実際に合格した人の学歴に関するデータはありません。しかし学歴は関係なく難易度が高いということは理解しておきましょう。
もしも大学が経済学部や地域関係の社会学部などで不動産に関する専攻をしていれば、ほかの受験者よりも有利に試験に臨めるかもしれません。
ほかの資格と比較した場合の難易度はどれくらい?
| 資格名 | 合格率 |
|---|---|
| 宅建士(宅地建物取引士)試験 | 15.6% |
| マンション管理士 | 8.6% |
| 日商簿記検定2級 | 26.9% |
不動産関連のほかの試験と、一般的に認知度の高い試験を2つ比較してみました。
マンション管理士の試験はとても難易度が高くわずか8.6%の合格率です。不動産業やマンション管理業で働く会社員が多く受験していて、7割以上の人が宅地建物取引士の資格も取得しています。専門的な知識が非常に重要とされるため、難易度が高いのもうなずける試験です。
一方で日商簿記検定2級は26.9%と宅建士の試験よりも10%程度高いことが分かりました。3級に比べ専門的な知識も増え学習時間の確保がより必要とされる日商簿記検定2級より、更に合格率が低いため、いかに宅建士の試験での勉強時間の確保が重要かが分かってきます。
社会人と大学生では合格の難易度が異なる?
次のデータはとある大学の経済学部で集計された資格取得に関する意識調査です。
| 資格名(一部抜粋) | 資格取得を目指している | 資格を取得している |
|---|---|---|
| ITパスポート | 14.9% | 2.9% |
| ファイナンシャル・プランナー | 38.3% | 2.9% |
| 宅地建物取引士 | 7.4% | 0.6% |
| 秘書検定 | 38.9% | 25.1% |
上記データを分析してみると、宅建士(宅地建物取引士)においては、社会人の方が有利である可能性も高いと言えるでしょう。
理由としては、以下の3つだと分析できます。
・ほかの資格に比べ、実際に取得している学生が0.6%とかなり少ない
・ほかの資格に比べ、資格取得を目指す同志が周りにいない
・社会人(とくに不動産業界で働く人)であれば、実務経験で理解しやすくなる
社会人と比べて学生で宅地建物取引士の資格を取得している人は0.6%と少ないです。学生であれば時間を有効活用できるというメリットがありますが、不動産関連の専攻を取得している学生でなければ簡単に理解することは難しいかもしれません。
また、ほかの代表的な資格に比べて取得を目指している学生も少ないです。同志が周りにいないとモチベーションを維持しづらく、分からないところを相談することもできないです。
こういった点から学生よりも社会人の方が独学において有利といえる可能性が高いです。
最新!宅建士の試験日程について
最後に、宅建士の試験日についてまとめました。
例年同じようなスケジュールになっているので、今後の受験を検討している方は、以下の日程を参考に試験対策を始めましょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 試験案内の配布 | 令和7年7月1日(火)〜7月15日(火) |
| 受験申込の受付 | 郵送:令和7年7月1日(火)〜7月15日(火) インターネット:令和7年7月1日(火)〜7月31日(木) |
| 試験日 | 令和7年10月19日(日)13時から15時まで |
| 合格発表 | 令和7年11月26日(水) |
【分析結果】宅建士(宅地建物取引士)のまとめ
当ページでは、宅建士(宅地建物取引士)の合格難易度について、調査した結果をまとめました。
冒頭でもまとめた内容ですが、復習としてもう一度ざっくり記載しておきました。
【当ページをざっくりまとめると…】
・宅建士は17%前後の合格率で難易度は高め
・4科目のうち出題は全50問、勉強時間は300時間程度確保がおすすめ
・不動産関連の資格の中では最初に取得されやすい資格
・一般的なほかの資格の中では合格率が低く難易度が高いとされる
・不動産業界で働いている社会人の方が実務経験から理解しやすく合格に有利
まずは資料請求をして、宅建士(宅地建物取引士)の講座について、料金や内容を確認してみることもおすすめです。
ちなみに「BrushUP学び(https://www.brush-up.jp)」というサイトであれば、資料を一括請求することもできるので、覚えておきましょう。