文部科学省が取り組んでいる「GIGAスクール構想」により、いまや日本の子どもたちの教育環境にデジタル端末は必須のツールとなっています。
「1人1台端末」の早期実現や、家庭でも繋がる通信環境の整備など、「GIGAスクール構想」におけるハード・ソフト・人材を一体とした整備を加速することで、災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ICTの活用によりすべての子供たちの学びを保障できる環境を早急に実現
(引用:GIGAスクール構想の実現へ 令和2年度追補版|文部科学省)
とくに令和2年度(2020年)は新型コロナウイルス感染症のまん延防止等重点措置の影響で、日本中の学校でも自宅でのリモート学習が急務の対策事項となっていました。
文部科学省によると、2021年時点の全国の公立小・中学校での端末利用率は95%を超えており、ほとんどの小中学生が学校でタブレットを使った学習を進めているようです(例えば埼玉県では、さいたま市を除く62市町村の全1,041校でタブレット端末などを用いたCBT形式が実施されています)。
しかし、高校生に関しては導入がそこまで進んでいません。
旺文社による高等学校への調査によると、2022年時点でタブレット端末の利用率は69.8%と、小中学生よりも大きく下回る結果であることが分かりました。
この件については文部科学大臣・デジタル大臣からも、「高等学校における1人1台端末の環境整備」を急ぐための協力を呼びかける声明を発表しています。
高校生については各自治体によって学校でタブレット端末をどう導入するべきかの対応が異なり、東京都では端末購入における補助金制度を設けていますが、埼玉県では家庭での自己負担をお願いしている状況です。
せっかく自己負担で家庭がタブレット端末を用意するなら、家庭でも学習できるような環境を整えておきたいですよね。
実際に、学校と自宅でのタブレット学習を両立できるよう支援している自治体も多くあります(参照:文部科学省)
そこで今回の記事では、高校生の家庭学習に通信講座を取り入れたいご家庭向けに、タブレット学習のメリット・デメリットや、おすすめのタブレット学習サービスを紹介していきます。
 小山先生
小山先生最後までチェックして、ご家庭でもタブレット学習ができる環境整備を検討してみてください!
高校生におすすめしたいタブレット学習サービスTOP7
早速おすすめのタブレット学習サービスTOP7を紹介していきます。
一つずつ詳しく見ていきましょう!
【調査の説明】
高校生向けタブレット教材の調査は、リサーチ部門がある株式会社イードが運営するミツカル教育通信編集部により実施されています。
ミツカル教育通信は教育情報サイト”リセマム“のグループブランドとして、子供教育に特化したメディアです。
なお、ミツカル教育通信の運営会社である株式会社イードは東京証券取引所にてグロースしている上場企業(証券コード:6038)となります。
※2026年1月現在、調査項目の更新・確認済み
高校生向けタブレット教材のランキング根拠はこちら
 自分の弱点を克服できる定期テスト対策がしたいなら「スマイルゼミ」
自分の弱点を克服できる定期テスト対策がしたいなら「スマイルゼミ」

ランキング評価
-
- 受講費用
- 5
-
- 対応科目
- 5
-
- カリキュラム
- 5
-
- サポート体制
- 5
-
- 管理機能
- 4
| 受講費用 | |
|---|---|
| 対応科目 | |
| カリキュラム | |
| サポート体制 | |
| 管理機能 | |
| 総合評価 | 24/25点 |
スマイルゼミは教科書準拠で対応科目数も幅広いことから、学校の定期テスト対策にぴったりのタブレット学習サービスです。
専用タブレットが必要になりますが、そのタブレットの中には専用カリキュラムを作るAIコーチシステムや暗記カード・ドリルといった専用コンテンツが多数収録されています。
プログラミング言語にも対応しているので、学校の定期テストでは全教科頑張りたい高校生におすすめです。
対象期間中に「高校生コース」の資料請求をすると、素敵なプレゼントがもらえるキャンペーンを実施中です。
▼対象期間
2026年1月16日(金)~2026年2月12日(木)
▼高校生コース:資料請求特典
ディズニーデザインステッカー
おすすめのコースと使い方
- 学校のテスト範囲と試験日程を登録して自分専用のテスト対策カリキュラムを作る
- Androidモードに変えて勉強した分のポイントで勉強の息抜きをする
- ペースメーカーとして季節講習を受講して自分の弱点を短期間に克服する
基本情報
| 受講料金(税込) | 17,380円~(12ヶ月分一括払い) |
| オプション料金(税込) | 英語プレミアム:3,278円/月~ タブレットあんしんサポートパック:3,960円/年 |
| 1回あたりの学習時間 | 1回15分~ |
| コース・目的 | 授業対策 定期テスト対策 入試対策 |
| 対応科目 | 科目数:7(英・数・国・理・地歴・公・情報) 教科書準拠:〇 |
| 4技能・プログラミング対応 | 4技能:〇 プログラミング:〇(情報) |
| 専用タブレット | 〇(10,978円) |
| 実績 | 2023年度大学合格実績 筑波大付属/青山学院高等部など |
| 学習機能 | 戦略AIコーチ(AI分析システム) 自分専用テスト対策プラン 暗記カード 漢検ドリル 5分トレーニング 季節講習 |
| サポート内容 | 保護者向けみまもるネット ポイント制度 Androidモード |
| 無料体験 | あり |
| 運営会社 | 株式会社ジャストシステム |
| 公式キャンペーンページ | https://smile-zemi.jp/koukou/lp/catalog/ |
 自分に合った大学受験対策を行いたいなら「進研ゼミ高校講座」
自分に合った大学受験対策を行いたいなら「進研ゼミ高校講座」

ランキング評価
-
- 受講費用
- 5
-
- 対応科目
- 5
-
- カリキュラム
- 5
-
- サポート体制
- 4
-
- 管理機能
- 4
| 受講費用 | |
|---|---|
| 対応科目 | |
| カリキュラム | |
| サポート体制 | |
| 管理機能 | |
| 総合評価 | 24/25点 |
進研ゼミ高校講座は、通常の定期テスト対策から受験対策まで幅広い目的に対応するコースやカリキュラムを提供しています。
とくに受験対策は志望校のレベル別に3コースに分けていて、最難関の東大・京大レベルの入試対策もバッチリ行えるのが特徴です。
必要に応じて小論文や記述問題対策の講座も受講できるほか、自分の弱点克服に合わせた大学受験対策の個別カリキュラムを作成してもらったり、必要に応じて進路指導のプロや先輩からアドバイスをもらえたりなど、高1からの受験対策にも手厚く対応してくれます。
おすすめのコースと使い方
- 追加料不要のまなびライブラリーで1,000冊の本+20本の動画から興味・関心を引き出す
- 志望校の出題内容やレベルに合わせて追加オプションの講座を受講する
- 全教科チェックできるアプリを使ってスキマ時間にインプットさせる
基本情報
| 月額料金(税込) | 6,480円~ (高1講座8月号入会・12ヶ月一括払いの場合) |
| オプション料金(税込) | 小論文特講:17,800円 記述添削特講:9,450円~ 過去問添削特講:19,900円 オンラインスピーキング:2,780円/月 ゲーム型英語学習アプリ:980円/月 |
| 1回あたりの学習時間 | 1回5分~ |
| コース・目的 | 最難関大挑戦コース 難関大挑戦コース 大学進学総合コース 授業 テスト対策 |
| 対応科目 | 科目数:5(英・数・国・理・地) 教科書準拠:〇 |
| 4技能・プログラミング対応 | 4技能:〇 プログラミング:〇(高1・2の情報・実技) |
| 専用タブレット | ✖ |
| 実績 | 2023年度大学合格実績 国立大:8,246人 私立大:30,352人 推薦入試:9,166人 |
| 学習機能 | AI StLike(AI分析システム) 予習復習効率UPアプリ 速攻Q暗記 紙テキスト(チャレンジ) |
| サポート内容 | 進研模試対応 大学合格逆算ナビ 24時間教科質問サービス 合格戦略アドバイス(プロの個別相談 月3回) 先輩ダイレクト(大学生への質問掲示板) まなびライブラリー お友だち・ごきょうだい紹介制度 |
| 無料体験 | あり |
| 運営会社 | 株式会社ベネッセコーポレーション |
 入試対策で小論文や英語4技能まで強化したいなら「Z会」
入試対策で小論文や英語4技能まで強化したいなら「Z会」

ランキング評価
-
- 受講費用
- 5
-
- 対応科目
- 5
-
- カリキュラム
- 4
-
- サポート体制
- 4
-
- 管理機能
- 4
| 受講費用 | |
|---|---|
| 対応科目 | |
| カリキュラム | |
| サポート体制 | |
| 管理機能 | |
| 総合評価 | 23/25点 |
Z会は主に受験対策をメインに取り扱うタブレット学習サービスです。
もとは紙テキストでの通信講座がメインだったため、現在もテキストと併用してタブレット学習を進められます。
小論文科目が用意されていてしっかりとした記述添削のサービスを受けられるほか、共通テストから推薦入試、個別大学試験の対策までさまざまな入試スタイルに合わせた対策を提供。
2023年だけでも1,000人以上が東大・京大などの難関大学に合格した実績を残しているので、難易度の高い大学への受験を検討している高校生は入会を検討してみてください!
おすすめのコースと使い方
- 志望校の難易度に合わせた個別試験対策で添削指導を受けて得点力を伸ばす
- 記述リプレイ機能を使って記述問題の作成する思考を養う
- 英語4技能をまんべんなく伸ばしたいならAsteriaにして本格的な英語レッスンを受ける
基本情報
| 月額料金(税込) | 3,650円~ |
| オプション料金(税込) | Asteria:要問合せ タブレット補償サービス:200円/月 |
| 1回あたりの学習時間 | 1回30分~ |
| コース・目的 | 個別試験対策 共通テスト対策 推薦入試対策 |
| 対応科目 | 科目数:7(英・数・国・理・歴・地理・小論文) 教科書準拠:✖ |
| 4技能・プログラミング対応 | 4技能:〇 プログラミング:✖ |
| 専用タブレット | 〇(iPad可、24,900円) |
| 実績 | 2023年度大学合格実績 東大:1,263人 京大:1,010人など |
| 学習機能 | AI速攻トレーニング 紙教材併用 記述家庭リプレイ機能 英語アセスメントテスト |
| サポート内容 | 添削指導 質問対応 進捗管理機能 |
| 無料体験 | なし |
| 運営会社 | 株式会社Z会 |
4位:不登校や発達障がいの高校生で学校の授業に追いつきたいなら「すらら」

ランキング評価
-
- 受講費用
- 4
-
- 対応科目
- 5
-
- カリキュラム
- 4
-
- サポート体制
- 4
-
- 管理機能
- 4
| 受講費用 | |
|---|---|
| 対応科目 | |
| カリキュラム | |
| サポート体制 | |
| 管理機能 | |
| 総合評価 | 21/25点 |
すららは小学校から高校の範囲までを無学年に学べるオンライン学習システムで、全国の教育機関や塾でも導入されています。
ゲーミフィケーションで飽きることなく学習を続けられるほか、AI搭載型ドリルで自分の理解度に合わせた問題が出題されるので、基礎力をしっかり伸ばせます。
高校で現在不登校気味の学生でも、学校の進度に追いつけるようにすららコーチがサポートしてくれるので、保護者も安心して活用できる学習システムです。
おすすめのコースと使い方
- 現役塾講師の「すららコーチ」に科目の質問や学習の進め方について悩みを相談してみる
- 基礎力が足りていないと感じる科目は小学校や中学校の範囲にさかのぼってやり直す
- 定期テスト制度を使って自分の弱点を理解したうえで学習を進めていく
基本情報
| 月額料金(税込) | 8,228円~ |
| オプション料金(税込) | 入会金:7,700円~ |
| 1回あたりの学習時間 | 15分程度 |
| コース・目的 | 基礎力強化向け 中高一貫対策向け 不登校向け 発達障がい向け 海外子女向け |
| 対応科目 | 科目数:5(英語・数学・国語・理科・社会) 教科書準拠:✖ |
| 4技能・プログラミング対応 | 4技能:〇 プログラミング:✖ |
| 専用タブレット | ✖(PC可) |
| 実績 | ― |
| 学習機能 | AI搭載型ドリル 定期テスト機能 テスト制度(小テスト/診断テスト) ゲーミフィケーション機能 |
| サポート内容 | すららコーチの学習サポート |
| 無料体験 | あり |
| 運営会社 | 株式会社すららネット |
5位:とにかく安いタブレット学習を希望するなら「スタディサプリ」

ランキング評価
-
- 受講費用
- 4
-
- 対応科目
- 4
-
- カリキュラム
- 4
-
- サポート体制
- 4
-
- 管理機能
- 4
| 受講費用 | |
|---|---|
| 対応科目 | |
| カリキュラム | |
| サポート体制 | |
| 管理機能 | |
| 総合評価 | 20/25点 |
スタディサプリはとにかく月額料金が安いため、手軽にタブレット学習を始めてみたい高校生のご家庭におすすめです。
文部科学省が発表した令和3年度の子どもの学習費調査によると、高校生の学校外での「補助学習費」にかける費用は、公立高等学校でひとり年間17.1万円、私立高等学校でひとり年間24.7万円でした。
いずれもだいたい月額1.5万円程度かけて家庭学習や塾などに通っているようです。
スタディサプリは月額3,000円以下で利用できるだけでなく、コーチング指導のある合格特訓コースをつけても1万円少しと、高校生の平均補助学習費用を下回る費用で受講できますよ。
基本情報
| 月額料金(税込) | 2,178円~ |
| オプション料金(税込) | 合格特訓:8,602円/月 |
| 1回あたりの学習時間 | 1回15分~ |
| コース・目的 | 授業対策 資格対策 合格特訓コース 共通テスト対策 |
| 対応科目 | 科目数:6(英・数・国・理・社・情報) 教科書準拠:✖ |
| 4技能・プログラミング対応 | 4技能:〇 プログラミング:△(情報) |
| 専用タブレット | ✖ |
| 実績 | 2022年度合格実績 東京大学、京都大学など |
| 学習機能 | 志望校向け学習プラン |
| サポート内容 | コーチによるカスタマイズ(合格特訓コースのみ) 月10回の質問対応(合格特訓コースのみ) 個別指導(合格特訓コースのみ) |
| 無料体験 | あり |
| 運営会社 | 株式会社リクルート |
6位:無駄な費用をかけずに基礎力を伸ばしたいなら「河合塾one」

ランキング評価
-
- 受講費用
- 4
-
- 対応科目
- 4
-
- カリキュラム
- 4
-
- サポート体制
- 4
-
- 管理機能
- 4
| 受講費用 | |
|---|---|
| 対応科目 | |
| カリキュラム | |
| サポート体制 | |
| 管理機能 | |
| 総合評価 | 20/25点 |
河合塾oneは大手予備校河合塾の手がけるオンライン学習サービスで、シンプルなコンテンツと必要に応じて追加できるトレーナーサポートが魅力的。
月額4,000円以下で基本の5科目のテキスト・映像講義とアウトプットコンテンツを利用できます。
ただし、国語に関しては古文のみ対応となるので注意してください。
月3回までならトレーナーへの質問も無料で、必要なサポートはしっかり基本料金に含まれているのが嬉しいポイントですね。
おすすめのコースと使い方
- AIおすすめ学習を使って効率よく自分の理解度を伸ばせる学習カリキュラムを実行する
- 毎月3回は疑問点を積極的にトレーナーに質問してみる
- トレーナーオプションを追加して分からないことや学習計画を気兼ねなく相談する
基本情報
| 月額料金(税込) | 3,939円~ |
| オプション料金(税込) | トレーナー:1,100円/月 月4回目以降の質問:550円/回 |
| 1回あたりの学習時間 | 1回5分~ |
| コース・目的 | 基礎力強化向け 定期テスト対策 |
| 対応科目 | 科目数:5(英語・数学・古文・理科・歴史) 教科書準拠:〇 |
| 4技能・プログラミング対応 | 4技能:✖ プログラミング:✖ |
| 専用タブレット | ✖(PC可) |
| 実績 | ― |
| 学習機能 | AIおすすめ学習 レベルチェックテスト 練習問題 単元受講前後テスト |
| サポート内容 | 月3回の無料質問サービス 保護者向けマイページ |
| 無料体験 | あり |
| 運営会社 | 株式会社河合塾One |
7位:無制限に質問をして疑問を解決したいなら「e点ネット塾」

ランキング評価
-
- 受講費用
- 4
-
- 対応科目
- 4
-
- カリキュラム
- 4
-
- サポート体制
- 4
-
- 管理機能
- 3
| 受講費用 | |
|---|---|
| 対応科目 | |
| カリキュラム | |
| サポート体制 | |
| 管理機能 | |
| 総合評価 | 19/25点 |
e点ネット塾は基礎力強化に特化したタブレット学習サービスで、年に6回の学力テストや3種類の学習補助テキスト配布など、独自の学習メソッドにこだわった学習環境を提供しているのが特徴です。
回数制限のない質問対応サービスは、5科目の基礎を抑えるうえで分からない疑問点をしっかり解消するのにぴったりのサポートと言えるでしょう。
基本情報
| 月額料金(税込) | 3,300円~ |
| オプション料金(税込) | ― |
| 1回あたりの学習時間 | 1回5分~ |
| コース・目的 | 基礎力強化向け |
| 対応科目 | 科目数:5(英語・数学・国語・理科・社会) 教科書準拠:✖ |
| 4技能・プログラミング対応 | 4技能:✖ プログラミング:✖ |
| 専用タブレット | ✖(PC可) |
| 実績 | ― |
| 学習機能 | 学習カルテ機能 全国一斉学力テスト 学習補助テキスト |
| サポート内容 | 無制限の質問対応 |
| 無料体験 | あり |
| 運営会社 | 株式会社 日本学術講師会 |
高校生にタブレット学習は効果的?タブレット学習のメリット3つを紹介

あらためて、今回のランキング結果は以下のようになりました。
しかし、高校生にとってタブレット学習を行うことにどんな効果があるのでしょうか。
まずは、タブレット学習のメリットと向いている高校生の特徴についてお伝えします。
- 通学中などのスキマ時間を使ってコツコツと学習を進められる
- 教材はすべてタブレットの中に収録されるので問題集や参考書がかさばらない
- タブレットに搭載される学習AIなどの機能で効果的な反復学習や弱点克服ができる
それぞれについて詳しくチェックしていきましょう。
①通学中などのスキマ時間を使ってコツコツと学習を進められる
高校生にタブレット学習をおすすめする最大の理由は、通学中などのスキマ時間を有効に使ってコツコツ学習を進められることです。
高校生は学業だけでなく部活動やアルバイトなど、多忙なスケジュールを抱えています。
タブレット学習サービスはオンライン環境が必要なケースが一般的ですが、モバイルルーターやスマホのテザリングでインターネットに接続できれば、通学中の電車やバスの車内でも手軽に学習を進めることが可能です。
また、サービスのなかにはオフラインで利用できたりスマホのアプリと連携できたりなど、さらに手軽に使いやすいタブレット学習サービスもあります。
 小山先生
小山先生塾や家庭教師のように決まった時間が固定されることもなく、自習が苦手な高校生でも無理のないペースで続けられるでしょう。
②教材はすべてタブレットの中に収録されるので問題集や参考書がかさばらない
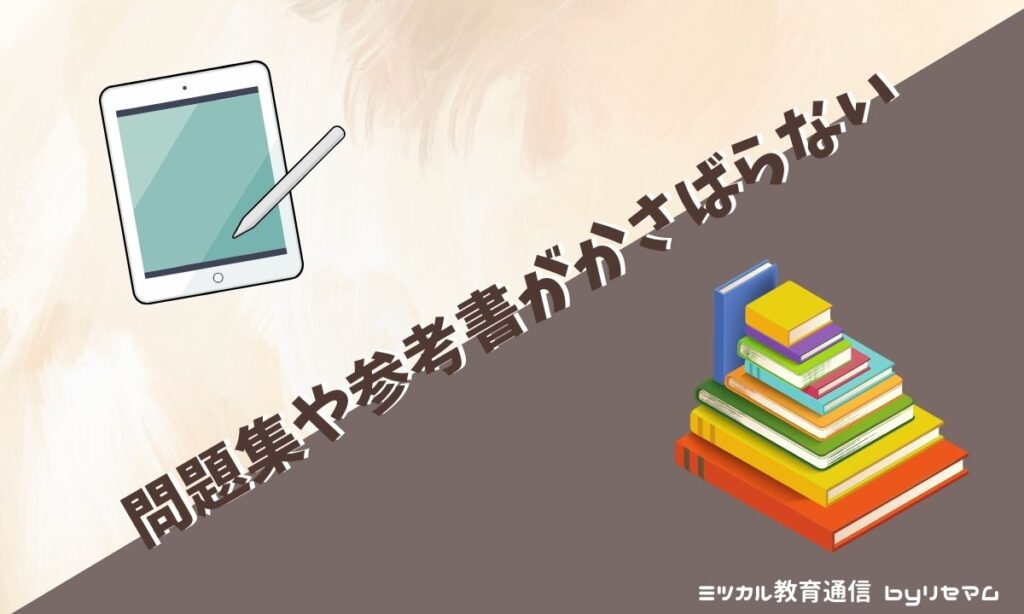
タブレット学習では、必要な教材や問題集などは基本的にデジタルコンテンツとしてタブレットの中で提供されます。
タブレット1台があれば全教科のテキストや問題集にいつでもアクセスでき、持ち運びにも便利です。
図書館やカフェで気分転換に勉強をしたい時も勉強したい科目の教材をすべて持ってくる必要もありませんし、部屋の中に教材がどんどんと溜まっていく心配もありません。
冊子版とはちがって紙の資源を使わないため、環境にもやさしい学習環境と言えるでしょう。
デジタルコンテンツといえども、サービスによっては教材をすべて網羅した検索機能や、自分で好きにマーカーやメモを追加できる機能もあります。
一度書き間違えたメモも消せるので、紙教材への書き込みよりも効率よくポイントの強調やまとめができますよ。
③タブレットに搭載される学習AIなどの機能で効果的な反復学習や弱点克服ができる
タブレット学習サービスによっては学習AIが搭載されていて、これにより効果的な反復学習や弱点を克服できる問題の提出が可能となっています。
一人ひとりの特性に寄り添ったカリキュラムを提案してくれるので、周りと同じカリキュラムで進める学校よりも、さらに効果的に学力を伸ばすことが期待できます。
タブレット学習では学習データとして進捗状況や理解度を逐一分析し、強みと弱みを正確に捉えてくれます。
そしてカスタマイズした学習計画をもとに適切な問題を出題してくれるので、自分で復習する問題を選ぶ必要もありません。
反復学習で記憶が定着するまで、過去の学習履歴に基づいて適切なタイミングでの出題を繰り返してくれます。
 小山先生
小山先生その日にどんな問題に取り組むべきか考える時間がなくなるので、よりインプット・アウトプットに時間をかけられる環境です。
高校生にはお金の無駄になる?タブレット学習のデメリット3つを紹介

メリットが多くあるタブレット学習ですが、一方で知っておきたいデメリットも。
- 自発的に取り組まないと進まない・集中力が続きにくい
- 眼精疲労や姿勢の悪化など身体的に悪影響があるリスクも
- 学校のタブレットとは別に専用タブレット代がかかる可能性
それぞれについて詳しくチェックしていきましょう。
①自発的に取り組まないと進まない・集中力が続きにくい
高校生のタブレット学習は効率よく学習できる点でメリットがある一方で、自主性が求められる環境である点には注意が必要です。
毎日忙しい高校生にとって、スキマ時間は自由時間にもなります。
そんな時に「タブレットで学習しよう」と自発的に取り組める高校生でないと、メディアの誘惑も多い状況下のスキマ時間に学習をコツコツと進めるのは難しいでしょう。
とくにタブレットを使っていると学習コンテンツ以外のアプリもあり、SNSやゲームといった楽しいコンテンツももちろんあります。
効率よく学習したい家庭にとってこれらの誘惑要素は進捗を妨げる要因にもなり、途中で集中が切れて遊んでしまう可能性も。
また、紙ノートに書き込む時とタブレット端末に書き込むと時の脳波の動きを調査した論文(波多野ほか、2015)によると、タブレット端末に書き込んでいる時のほうが、書字行動自体に注意を奪われている傾向があることが分かりました。
書くことに集中してしまい、文章読解や理解において紙ノートのほうが有効になるケースがあるようです。
 小山先生
小山先生つまり、タブレット学習で成果を出すためには、高校生自身が自発的に学習をコツコツ続けられること、学習時間はしっかり集中できることが必要となります。
②眼精疲労や姿勢の悪化など身体的に悪影響があるリスクも

身体的なデメリットとして、目や姿勢への悪影響も考えられます。
長時間デバイスを使って学習をすると、目の疲れやドライアイのほか、首や背中への負担が増す可能性もあるでしょう。
タブレット学習をする際は、適度な休憩時間を設けて置いたり、画面と適切な距離感を保って学習することが必要です。
また、タブレットによってはブルーライトカットができるディスプレイ表示設定を搭載しているものもあるので、必要に応じて保護者や高校生自身がタブレットの設定を変えてみるのもよいでしょう。
③学校のタブレットとは別に専用タブレット代がかかる可能性
自治体によっては学校で使うタブレット端末を家庭学習向けに利用してもよい、としているところもありますが、学校によっては併用を禁じている可能性もあります。
この場合、学校で使用するタブレットとは別にタブレット端末を用意しなければならず、追加の出費がかかる点においては家庭も注意深く意識しておく必要があるでしょう。
さらにタブレット学習サービスによっては専用タブレットでないと利用できないケースもあるので、自治体で併用OKの場合でも、サービス次第で追加の端末代がかかることは理解しておきましょう。
気になるサービスが決まったら、入会前に学校側にタブレットの併用がOKか確認してみてください。
また、専用タブレットが必要な場合は、キャンペーンなどで端末代がお得にならないかチェックしておくことも大切ですよ。
高校生に効果的なタブレット学習サービスの選び方5つを紹介
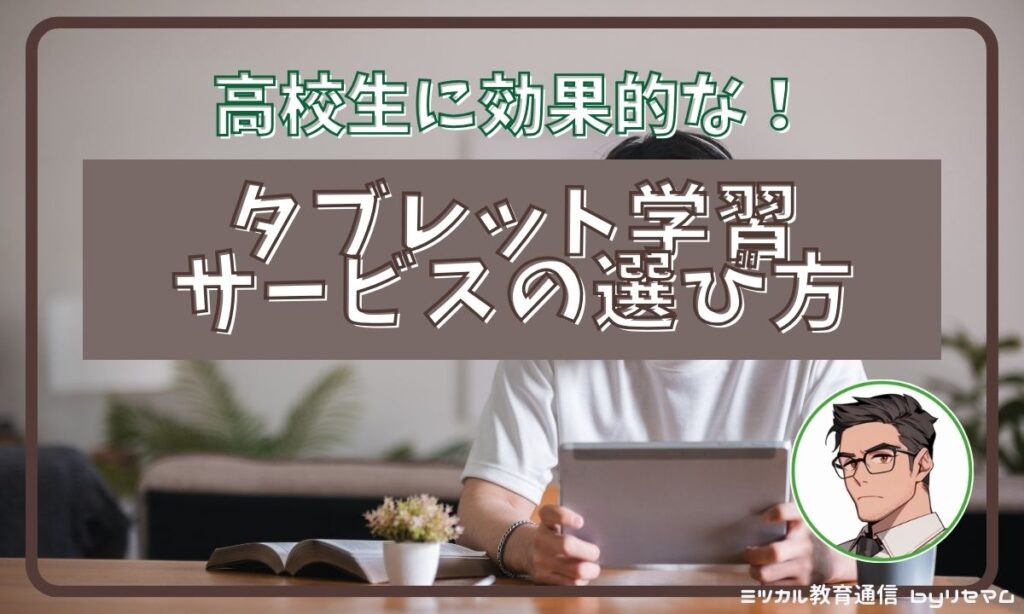
高校生にとってタブレット学習にどんなメリット・デメリットがあるか確認した後は、サービスを選ぶ時に知っておきたい選び方をチェックしましょう。
- レベルや学習する目的に合ったコース・教材があるかチェック
- 有料オプションの追加などを想定した予算を設定して料金を比較する
- 学習中の疑問や不安を解消できるサポート体制があると安心
- 受験対策に対応していても対策の難易度は確認しておこう
- キーボード付きのタブレットを利用できるとなお良し◎
それぞれ細かく選び方を見ていきましょう。
①レベルや学習する目的に合ったコース・教材があるかチェック
高校生の学習する目的は人によってそれぞれ異なるため、選択できるコースや教材は豊富であると選びやすいでしょう。
たとえば大学受験を目的に学習したい生徒には、志望校対策コースがあるとより効率よく学習計画を立てられます。
教材で取り組むテーマについても、学習モチベーションが維持できるようなトピックを取り扱う教材があるとなおよいでしょう。
無料お試し期間にさまざまな教材をチェックしておき、自分に合っているか確かめてみることがおすすめです。
②有料オプションの追加などを想定した予算を設定して料金を比較する
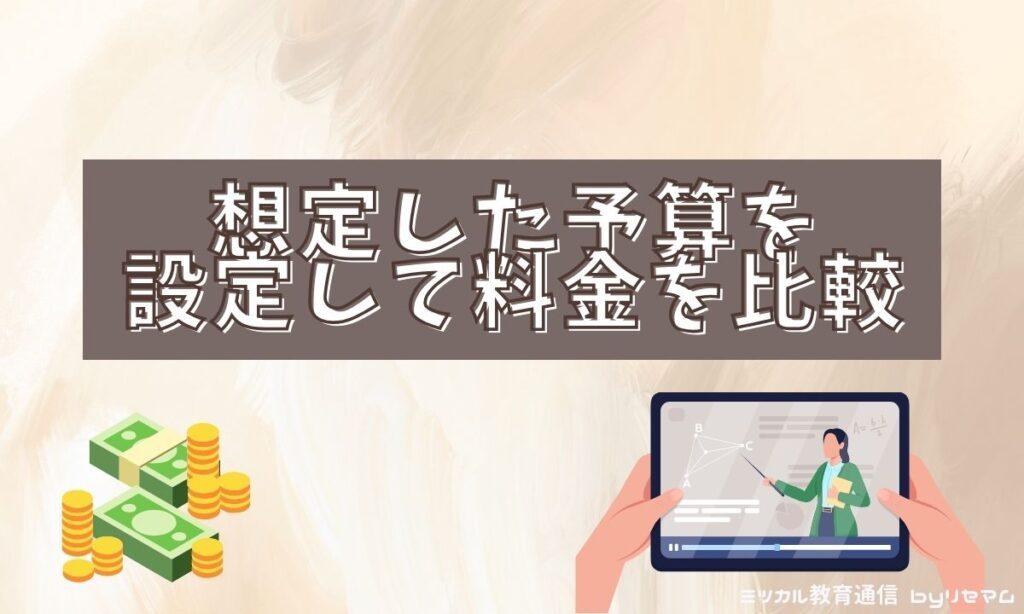
高校生向けタブレット学習では、基本の月額料金プランだけでなく、有料オプションや追加のサービスも状況によって必要となってきます。
たとえばマンツーマンのコーチング指導や模擬試験の追加受験、プログラミングなどの追加科目を受講したい時は、追加費用がかかるケースがあります。
月額料金が安いから契約するのではなく、保護者と高校生でどんなサポートを受けたいか・どんな講座を受講したいかをしっかり話し合って決めた上で、最終的な予算を確認しておきましょう。
③学習中の疑問や不安を解消できるサポート体制があると安心
高校生自身が利用したいと思えるサポート体制が実装されているかは確認しておくべきです。
高校生がタブレット学習を進めている時、学習における疑問点や進路への不安が生じることはよくあるでしょう。
その時に信頼できるサポート体制を利用できるかは選び方においても重要なポイントです。
専門的な教育知識や指導経験が豊富な人によるアドバイス・質問対応のサポートがあると安心できます。
 小山先生
小山先生また、オンラインコミュニティなどでほかの学習者による質疑応答も確認できるサービスがあると、自分以外にも悩みを抱えている高校生がいると分かって不安も減らせるかもしれません。
④受験対策に対応していても対策の難易度は確認しておこう

タブレット学習を利用開始するタイミングで、すでに受験対策を意識している高校生も多いのではないでしょうか。
受験対策に対応するタブレット学習サービスは多くありますが、その難易度は志望校によって異なります。
そのため、どれくらいの志望校レベルまで受験対策が対応できているかは必ずチェックしてください。
地元の国立・私立大学で過去問傾向分析ができているカリキュラムもあれば、旧帝大や有名私立大の一般入学を見据えた受験対策を展開するカリキュラムもあり、同じ受験対策と言ってもその難易度は大きく変わってきます。
また、医学部など特定の難関学部を受験したい場合も、自分の今の理解度と必要なレベルまでに到達するための適切なカリキュラム作成が求められます。
タブレット学習サービスのなかにはこれまでの学習データを分析して、より一人ひとりの希望に沿ったカリキュラム作成を実現できるものもあります。
しかし、中には大学受験対策としてはあまり有効に活用できない教材もあるので、コースと難易度には注意してください。
⑤キーボード付きのタブレットを利用できるとなお良し◎
高校生のタブレット学習においては、キーボードを追加できる端末だと扱いやすくなります。
試験対策の中には長文の記述問題や論文問題が出題されることもあり、手書きで書き込むよりもキーボードのほうが時間削減の効果を期待できます。
また、キーボードをよく利用することでタイピングスキルも向上し、将来的に働く上で求められるパソコンスキルにも繋がります。
専用タブレットの場合、キーボードを取り付けられるか確認してみるのもよいでしょう。
 小山先生
小山先生また、場面に応じてキーボードをサッと取り外せるものを選んでおくと、より使いやすくなります。
高校生が知っておきたい効果的なタブレット学習の使い方をチェック
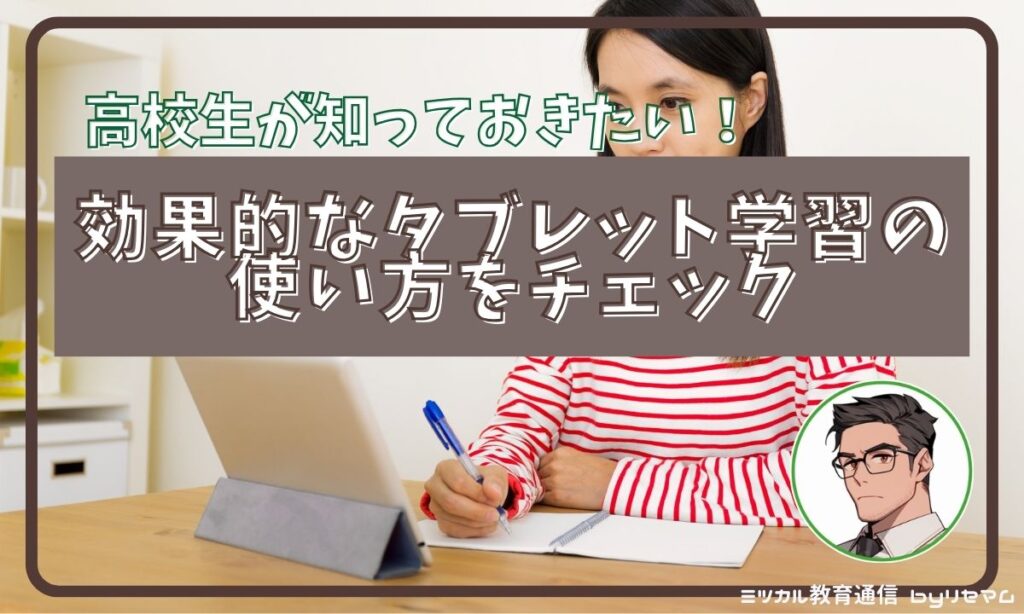
高校生が自宅学習でタブレット学習を活用したい時に、効率よく弱点克服や試験対策ができる使い方を紹介していきます。
- まずは明確な目的・目標を設定してから学習計画を立てる
- タブレット学習を習慣化して毎日のルーティンに取り入れる
- 学習進捗・成績をチェックして定期的に学習計画を見直す
それぞれ細かく選び方を見ていきましょう。
①まずは明確な目的・目標を設定してから学習計画を立てる
まずはタブレット学習を受講する最大の目的がなにかを明確にしましょう。
「受験対策」「定期テスト対策」など大まかな目的を明らかにしたうえで、どの科目で何点アップさせたいのか目標を設定してください。
目標をいつ達成するのかスケジュールを決めたら、学習を開始してからゴールの日程までにどれくらいの学習時間を確保できるか具体的に算出してみてください。
月や週単位で算出すると、毎日同じ学習時間を確保できなくても週末などに調整がしやすいですよ。
そして、タブレット学習を使って具体的にどんなスケジュールで学習を進めていくか計画を立ててみましょう。
 小山先生
小山先生サービスによってはゴールの日程と目標を設定することで自動的に学習カリキュラムを作成してくれるものもありますが、こういったサービスも活用していきながら自分に合った学習計画を策定してみてください。
②タブレット学習を習慣化して毎日のルーティンに取り入れる

学習計画を立てただけでは学力は伸びず、もちろん実行していくことが大切です。
タブレット学習のデメリットとして「自発的な姿勢が求められる」ことを挙げましたが、タブレット学習は習慣化してコツコツ取り組むことをおすすめします。
たとえば通学中や帰宅後手を洗ってから着替える前になど、自分が取り組みやすい時間帯に学習をするルーティンを作ることで自然と習慣化していきます。
また、集中できるように自宅内でも学習用スペースを用意したり、自宅に帰る前に近くの図書館に立ち寄って学習するなど、学習環境にも気を配ることが大切です。
タブレット学習サービスによっては進捗が見える化されているものもあるので、自分の頑張りを逐一チェックしてモチベーションを維持しながら毎日続けてみてください。
③学習進捗・成績をチェックして定期的に学習計画を見直す
モチベーションの維持や効率よく学習を続けるためのポイントとして、定期的に進捗や成績をチェックすることと、必要に応じて計画を見直すことをおすすめします。
毎週や毎月、どれくらいの時間を学習に充てていたのかを振り返ったり、日々のテストや定期的な模擬試験などで成績を確認することで、自分の理解度の伸びや弱点も見つけられます。
達成感を感じることでモチベーションもアップしますし、自分が気付かないうちにニガテ意識ができている単元も分かってくるので、定期的な自己評価や振り返りは必要です。
【FAQ】高校生におすすめしたいタブレット学習に関するよくある質問
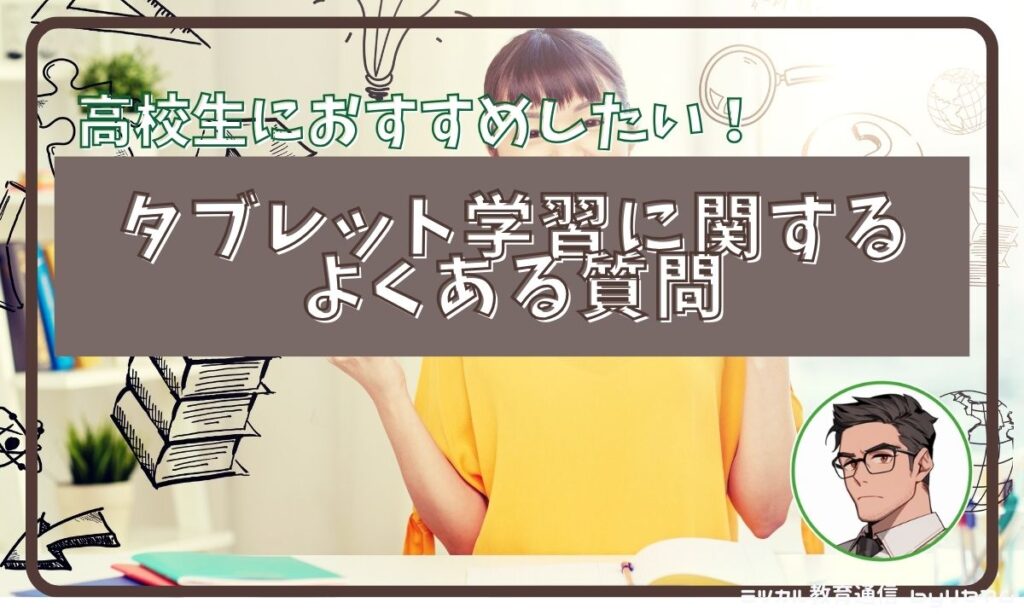
最後に、高校生におすすめしたいタブレット学習に関するよくある質問をまとめてみました。
高校生がchatGPTなど生成AIを使って学習することは可能?
今ではパソコンスキルの高い高校生も多いため、生成AIを活用して自主学習をしようと考えている人もいるでしょう。
黎明期でもある生成AIの教育段階での利用について、2023年7月に文部科学省が暫定的なガイドラインを提示しています。
ガイドラインによれば、生成AIの活用は望ましい場面と望ましくない場面があるため、とくに学校での使用においては注意が必要とのこと。
ガイドラインで提示されている「活用が望ましい場面」とは以下のようなシチュエーションです。
- 生成AIの回答に誤りがあることを前提知識として理解したうえで使用し、生成AIの性質や限界について気づかせる
- チャットを使った英会話の練習相手として自然な会話フレーズを学ぶ
- 英会話で興味関心をもったテーマの英単語や例文をリスト作成する
学校向けのガイドラインではありますが、高校生であれば家庭学習でも上記のような使い方で生成AIを活用できるでしょう。
ちなみに、chatGPTの利用は13歳以上で、18歳未満は保護者の同意が必要です。
また、Bing ChatやBardは18歳以上を想定しており、高校生であればchatGPTのみ保護者の同意がなくても利用可能です。
とはいえ、実際に使いたい時は保護者や学校でICT関係に詳しい人に相談してから使いましょう。
専用タブレットが故障した場合は?卒業後や退会後は返却が必要?
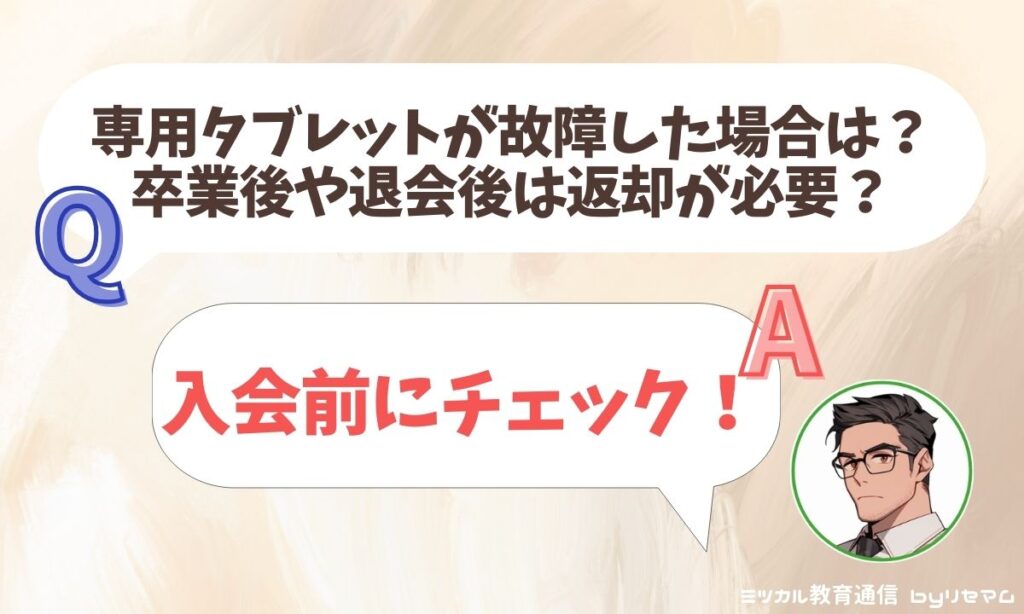
タブレット学習サービスが提供する専用タブレットが故障した場合は、まずカスタマーサポートに連絡してください。
修理や交換のサポートを受けることで解決することができますが、場合によっては一部の費用を負担する必要がある場合もあります。
具体的な自己負担額については、事前にカスタマーサポートに問い合わせて確認しておくことがおすすめです。
また、高校を卒業して退会する際には、通常、タブレットの返却が求められます。
返却の必要性については、入会前に確認しておくと安心です。
 小山先生
小山先生返却時にはデータリセットや初期化を求められることもあるため、必要な手順は退会前に問い合わせて確認してみてください!
高校生には家庭教師とタブレット学習どちらがおすすめ?
どちらがおすすめかは人それぞれ異なります。以下は家庭教師とタブレット学習それぞれのメリットです。
家庭教師のメリット
- 生徒1人ひとりのスケジュールに合わせた個別指導が可能で、送り迎えの必要もなし
- 特定の科目や難易度に合わせて学習内容をカスタマイズしてくれる
- 生徒が疑問に思ったことはその場で瞬時に講師に質問して解決できる
- 講師が生徒の目標や進度に合わせて学習計画を立案し、都度アドバイスをくれる
タブレット学習のメリット
- 講師側のスケジュールに合わせた指導を受ける必要がない
- 決まった学習時間を確保する必要がなくスキマ時間を活用できる
- 家庭教師に比べて費用を抑えてリーズナブルに学習ができる
- 家庭教師が対応できない科目の対応や、模擬テスト・問題集など豊富なコンテンツを利用できる
どちらを選ぶかは、学習の目的や予算、スケジュール、解決したいことなどの要素を踏まえて、家族と話し合いながら検討してみてください。
















