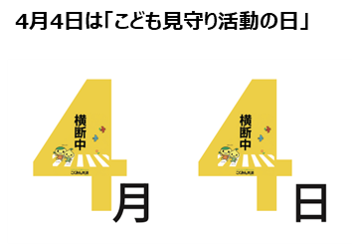
こくみん共済 coop 〈全労済〉(全国労働者共済生活協同組合連合会 代表理事 理事長:打越 秋一)は、未来ある子どもたちを交通事故から守っていく取り組み「7才の交通安全プロジェクト」を、2019年より実施しております。6年目を迎える本年度は、小学校の入学式直前となる4月4日を新たに「こども見守り活動の日」として記念日に制定し、この日を皮切りに、保護者やドライバー、学校関係者、地域が一体となって交通事故抑制に向けた意識を高め、みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくりに向けて活動することを発表いたします。
歩行中の交通事故の死傷者が多いのは、もうすぐ入学式を迎える“小学1年生”(7才)という、悲しい現実。未来ある子どもたちを交通事故から守る、「7才の交通安全プロジェクト」について
小学校にあがり行動範囲が広がる7才児は、大人よりも目線が低く、まだ十分に注意力が育まれていないために、歩行中の交通事故による死傷者数が突出して多いというデータがあります。(公益財団法人交通事故総合分析センター調べ)
そこで当会では、2019年3月に「7才の交通安全プロジェクト」をスタートし、今日に至るまで約155万本以上の「横断旗」を、全国の小学校・児童館などへ寄贈してきました。また、金沢大学融合研究域融合科学系の藤生慎教授と「私のまちの7才の交通安全ハザードマップ」を開発。子どもたちの交通安全についての研究・実験も行ってまいりました。
全国1,500名の生活者(大人)に、 「子どもと交通安全にまつわる実態・意識の調査」を実施!
今回の調査では、「交通安全・事故への意識」「子どもの交通安全の意識」「こども見守り活動の実態と意識」の3つの視点から、実態に迫りました。
調査結果トピックス
■約9割が「交通安全は大事」と答える。一方、「交通安全の知識」は記憶に残りづらく、定期的な学びが必要。
■親の約9割が“自分がいないときに、子どもが安全に行動できているか不安”と回答。求められる「見守りのあり方」とは?
■続いてほしいという声、8割超! 「こども見守り活動」が支える、子どもたちの交通安全。
1. はじめに - 「7才の交通安全プロジェクト」 発足背景-
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/65331/146/65331-146-418bdf286685ab063b808de0aaa53a8a-548x286.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
※参照
『小学校低学年児童の交通安全に関する基礎的研究
~7才児の交通事故発生件数に着目して~』より
交通事情の統計を調査する交通事故総合分析センターは、歩行中の交通事故による死傷者数で、7才児の死傷者数が際立って多い理由を「小学校への入学後に登下校中の事故が増加するためである」と推定しています。
具体的には、幼稚園や保育園までは保護者や園の関係者が送迎し、園から帰宅後も保護者が付き添って過ごす場合が多いものの、小学校入学とともに子どもたちだけで登下校を行い、また登下校中以外でもこの頃から子どもだけで行動する機会が増えるため、小学校入学を境に交通事故の発生リスクが高くなると考えられています。
交通安全教室などにより、子どもに交通ルールの啓発活動が行われてきましたが、頭では危険や予防策を理解していても、子どもの年齢が低いほど実際の安全行動につながりにくいのが現実です。登下校中の事故だけではなく、友だちと遊んでいるときや自転車に乗っている時の事故も多く、地域・社会が一体となって子どもたちを見守っていく活動の重要性が浮き彫りとなっています。
こうした実情を踏まえ、当会では「7才の交通安全プロジェクト」を発足。全国の小学校や児童館などへ横断旗の寄贈等を行ってまいりました。
2. 交通安全・事故への意識調査
Topics 1 約9割が「交通安全は大事」と答える。一方、「交通安全の知識」は記憶に残りづらく、定期的な学びが必要。
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/65331/146/65331-146-51d370e70ea45f85cc7a25d29cd1f66b-882x686.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/65331/146/65331-146-ab9c53b660bc76c6a2134438fd5d842c-878x684.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
まず初めに、「交通安全を意識したり、取り組むことが重要だと思いますか?」という問いに対し、
97.9%が「重要だと思う」「やや重要だと思う」と回答。ほぼすべての人が、その必要性を認識している結果となりました。
このような高い意識を背景に、実際の日常でどのような経験をしているのかにも着目し、「ヒヤリとした瞬間」の有無についても確認したところ...
53.4%が「自身や家族(兄弟姉妹やお子さんなど)が子どもの時に、自動車にぶつかりそうになってヒヤッとした」と回答。また、ドライバー100名の60.0%が「子どもとぶつかりそうになってヒヤッとした経験がある」と回答しており、リスクが“身近なもの”として存在する実態が浮かび上がりました。
加えて、交通事故防止に向けた取り組みとして行われている各種研修や啓発活動への参加状況と、その記憶の定着についても調査。交通安全に関する研修や活動について、 「自治体で実施している研修」に参加している人の半数は、研修に参加して2~3年以上が経つとその内容を忘れてしまうことなどが明らかになりました。
つまり、交通安全への意識や実体験がある一方で、その知識や行動が時間の経過とともに薄れてしまうリスクがあることも示唆されています。
だからこそ、いま一度「春の交通安全週間」などを活用し、定期的かつ繰り返しの情報発信や学び直しの機会を持つことが、交通安全の意識の維持において重要であることがわかりました。
3. 子どもの交通安全の意識調査
Topics 2 親の9割が“自分がいないときに、子どもが安全に行動できているか不安”と回答。求められる「見守りのあり方」とは?
[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/65331/146/65331-146-61f9e3da79497bbe8c6c9f82baa95af8-1962x866.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
続いて、「子どもの交通安全に関する意識」についても調査を行ったところ、実際に子どもの交通事故が起きる原因については、意外と知られていない事実が明らかになりました。
例えば、「飛び出し」や「子どもの注意力がまだ十分に育っていないこと」については、約8割が認識しており、多くの人が事故要因として理解している反面、今回のプロジェクトとも関連する「7才は他の年齢に比べて、交通事故に遭いやすい年齢である」 という事実については、認知している人は50.0%となり、(年長・小学1年生を含む)7才のお子さんがいる人でも、63.5%にとどまりました。
また、子どもの交通事故が発生しやすい“場所”についても、実は、事故の多くは「自宅から500m以内」で発生しているという事実(※)があるにもかかわらず、これを知らない人は全体の約6割にのぼりました。“自宅の周りだから安心”“いつも通る道だから大丈夫”と思いがちですが、むしろそうした “慣れた環境”こそ、子どもにとっても気の緩みが生じやすい場所であり、子どもを見守る親たちは気をつけたい場所と、言えるかもしれません。
※内閣府ホームページより( https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r03kou_haku/zenbun/genkyo/feature/feature_02_4.html )
[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/65331/146/65331-146-0d206d1a307bd6c81c8bc89d27bdb337-1750x826.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
次に、子どもの交通安全における「見守りのあり方」についても、調査からいくつかの気づきが得られました。
特に、小学生の子どもを持つ親の多くが、「自分がいないときに、子どもが安全に行動できているか不安(約9割)」「子どもだけで登下校させることにどこか不安を感じる(約8割)」といった思いを抱く、結果となりました。
こうした不安を背景に、フリーアンサー形式で「子どもの交通安全を守るためには何が必要か」について広く意見を募ったところ、以下のような声が寄せられました。
一般セル/男性50代
とにかく教育だと思います。自身を振り返っても子どものころは知識がないがゆえに危険な行動が多かったと思います。
今の安全意識の高い運転ができているのは、車に轢かれそうになった幼少時の記憶がすべてだと思っています。
一般セル/女性40代
子どもが1人で歩行通学、自転車通学をする時は初めて行く前に一緒に行き、危険ポイントを説明してきた。それは親として、みんながしてもらいたい。飛び出しなどしないようにも何度も言ってきたつもり。子どもが歩いている時は徐行している。見守りの旗当番の方には感謝しかありません。
一般セル/女性60代
子どもが公園に行く時は親も一緒に行って、他のお子さんのことも危険がないか見守ったり、学年を超えて近所の方とのコミュニケーションが日頃から取れるといいです。
一般セル/男性60代
こういう交差点はなんで危ないのかとか実際に現場で教え、車を運転する大人は常日頃から目線を低くして「かもしれない運転」で悲しい事故を防ぐ努力をドライバー全員で取り組んで欲しい。
など、子どもや親への教育、ドライバーへの取り組みといった対策のなかに、地域や自治体と協力しながら、大人が交差点などで旗を持ち、子どもの交通安全に取り組む「こども見守り活動」の重要性が、挙げられました。
4. こども見守り活動の実態と意識調査
Topics 3 続いてほしいという声、8割超! 「こども見守り活動」が支える、子どもたちの交通安全。
[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/65331/146/65331-146-3d34f8c80c4589f53ef8c689051c310b-1748x672.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
まず、 「こども見守り活動」に関する認知率は高く約9割となり、「詳細まで理解している」と答えた人は50.8%。「見聞きしたことがある程度」が39.9%、「見聞きしたことがない」が9.3%という回答となりました。
[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/65331/146/65331-146-a9f067e65aaaa345c0c02d5a56d8e64b-1750x786.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
実際に、「見守り活動が実施されている」と答えた7才のお子さんがいる人は88.8%、8-12才ののお子さんがいる人は95.7%と、ほとんどの学校で「こども見守り活動」が実施されていることがわかりました。その実施者については、保護者や地域のボランティアが活動を行うケースが約6割以上という結果となりました。
[画像8: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/65331/146/65331-146-f0f9f320ccfc2267c56ec66a189a8fbc-1752x660.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
また、「保護者によって実施されている」と答えた小学生のお子さんがいる人の約6割以上がこの活動に参加したことがあると回答。協力的なご家庭が大半であることがわかりました。
[画像9: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/65331/146/65331-146-89fb16b7a63bb829a8017e4481790d24-1752x772.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
そんな見守り活動についてのイメージを尋ねたところ、「この活動があることで何も起きない毎日が守られていると思う」「この活動がこの先も続いてほしい」「活動に取り組んでいる人に感謝の気持ちでいっぱい」 といった項目で、回答者の約8割以上が共感を示し、 「こども見守り活動」の重要性や感謝の思いが伝わる結果となりました。一方で、この活動に負担を感じる人も半数を超えることも明らかとなりました。
また「こども見守り活動」については、フリーアンサー形式でも保護者の声を募ったところ、日々の活動への感謝や、今後の継続を願うメッセージが数多く寄せられました。
一般セル/女性20代
車を運転しているものとして、子どもが赤信号できちんと止まるようにしてくれたり、逆に車をしっかり止めたりしてくれるので、子どもの近くを運転する時に安心して運転できます。日々の忙しい中で、決まった時間帯に決まった場所に立っているというのはとても大変だし、こういった活動はその方の善意で成り立っているものだと思っていますので、本当に感謝しています。いつもありがとうございます。
一般セル/女性30代
いつもたくさんの子ども達の安全を守ってくださりありがとうございます。時間帯的に社会人の若者が参加できることが少ないが、私たちの世代やその先にもずっと継続されていくような、このような活動を是非続けていただけたらと思います。
7才のお子さんがいる人/男性
いつもありがとうございます。みなさんのおかげで、子どもたちだけで登下校ができる社会になっています。
海外だと親が送り迎えすることが当たり前のような世の中で、信じられないような活動だと思います。
7才のお子さんがいる人/男性
子どもが小学校に通い始めて最も心配なのは、登下校の事故やトラブルでした。
なのでそれを未然に防ぎ、時には注意してくれる存在である旗振りの皆さんには大変感謝しています。
7才のお子さんがいる人/女性
自分の子どもはきっと社会に守られてお世話になっている部分が多いと思います。本当にありがとうございます。いろんな子や家庭があって活動していただく中で色々あるかと思います。きっと嫌な思いをされることも。それでもこの活動が続いているのは、全て、地域を良くしたい、子どもたちに少しでも安全な環境を提供したい、と思ってくれる大人の心だと思います。私としては、自分がこの活動に関わるのは当たり前の責任だと思っていますし、子どもが大きくなったら地域に恩返ししたいと思っています。
小学校教員
いつも本当にありがとうございます。高齢の方が多いので、今後はできる人ができる時に、積極的に参加できる世の中になってほしいし、そのためには、取り組みを発信していってほしいです。
小学校教員
日頃より子どもたちの安全に気を配っていただきありがとうございます。子どもたちはなかなか直接お礼を言ったり、すすんで「ただいま」と挨拶をしたりすることは少ないかと思いますが、「登下校の安全を守ってくれている人は?」と尋ねると、安全リーダーさんと答えることがほとんどです。
これからも子どもたちの安全のため、よろしくお願いします。
以上の結果を踏まえ、当会では「交通安全・事故への関心を高める発信」「子どもの交通安全のための情報提供」「こども見守り活動の理解促進とその活動への感謝と応援」に関する取り組みを推進していくとともに、社会環境の変化に伴った「こども見守り活動」にも取り組んでまいります。
調査名称:「子どもと交通安全にまつわる実態・意識の調査」
調査手法:インターネットアンケート
調査期間:2025年2月14日(金)~2月16日(日)
調査主体:こくみん共済 coop <全労済>
対象:全国1,500名の生活者(大人)
【内訳】
・20~69才の男女(一般セル):1,000名
・7才のお子さんがいる人:200名
(年長のお子さんがいる人:100名/小学1年生のお子さんがいる人:100名)
・8~12才(小学2-6年生)のお子さんがいる人:100名
・小学校教員:100名
・ドライバー(通学時間帯(平日の6~8時台/14~18時台)に運転):100名
5. 2025年度「7才の交通安全プロジェクト」の取り組みついて
今年度で6年目を迎える「7才の交通安全プロジェクト」。
さらなる取り組みの普及を目的に、当会は4月4日を「こども見守り活動の日」として記念日制定しました。(一般社団法人 日本記念日協会 認定)
また、横断旗の寄贈をはじめとした活動を通じて、「こども見守り活動」を継続して応援していくとともに、多くの方の目に留まり、この活動への理解と応援の声が集まるような取り組みを拡充してまいります。
4月4日は「こども見守り活動の日」
[画像10: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/65331/146/65331-146-d068a56fab5ada169741c368fb653d69-634x330.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
数字の「4」が“旗”の形に似ていることに加え、
小学校の入学式や春の交通安全週間が始まる直前というタイミングであることから4月4日を「こども見守り活動の日」に制定しました。
「こども見守り活動」に参加してくださっているすべての方々へ感謝を伝えるとともに、みんなで子どもたちを見守る社会を応援していくきっかけの一つになることを願っております。
<2025年度のアクション(予定)>
[表: https://prtimes.jp/data/corp/65331/table/146_1_0c65ca7c119cfe1ec265cafcd6b8db66.jpg ]
<4月4日~ プロジェクト動画公開WEBサイトURL>
https://www.zenrosai.coop/anshin/7pj/community.html
【参考】これまでの主な取り組み
(7才の交通安全プロジェクトサイト: https://www.zenrosai.coop/anshin/7pj.html)
1.横断旗の寄贈
共済商品の利用を社会課題の解決にも繋げるため、2020年6月より「マイカー共済」のお見積もり1件につき、1本の横断旗を寄贈する取り組みをスタートしました。これまでに約155万本以上の横断旗を全国の児童館・小学校などへ寄贈することができました。
2.交通安全デジタル絵本を公式サイトで公開
子どもと親の交通安全意識を高めることを目的に、親子で楽しみながら交通安全について学ぶことができるデジタル絵本「ふしぎなふしぎなマジカルメガネ」を公式サイトで公開しています。
3.金沢大学との共同研究の実施
2019年11月から、金沢大学との共同研究をスタートし、7才児を中心に子どもたちの目線や行動を調査して、交通事故から子どもを守るための具体的な実験・分析と改善に取り組んでいます。
4. 「私のまちの7才の交通安全ハザードマップ」を公開
こくみん共済 coop が金沢大学・藤生教授と開発。お出かけ前に、これから通る道で過去に起こった事故の情報を調べたり、私たちのまちを
より安全なまちにするために、危ない場所や交通安全の取り組みを行っている場所を投稿することができます。
ご家庭や学校での交通安全教育にお役立ていただければ幸いです。
<こくみん共済 coop >
正式名称:全国労働者共済生活協同組合連合会
たすけあいの生協として1957年9月に誕生。「共済」とは「みんなでたすけあうことで、誰かの万一に備える」という仕組みです。
少子高齢化社会や大規模災害の発生など、私たちを取り巻く環境が大きく変化しているなか、こくみん共済 coop は、「たすけあい」の考え方や仕組みを通じて「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」にむけ、皆さまと共に歩み続けます。
◆こくみん共済 coop たすけあいの輪のあゆみ: https://www.zenrosai.coop/web/ayumi/
[画像11: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/65331/146/65331-146-426c4774a371219dfa7058a2c6aae23b-1378x1378.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
国連は、持続可能な生産と消費、食料安全保障、気候変動対策、地域の人々への医療・福祉、働きがいのある人間らしい仕事の創出、すべての人が参加できる社会づくりなど、さまざまな分野で持続可能な開発目標(SDGs)に貢献している協同組合を評価し、その認知の向上と協同組合の振興のために、2025年を国際協同組合年(International Year of Cooperatives:IYC)に定めました。
こくみん共済 coop はIYC2025に賛同しています。
https://www.zenrosai.coop/zenrosai/profile/kokusai/iyc/2025.html
プレスリリース提供:PR TIMES

