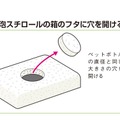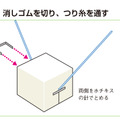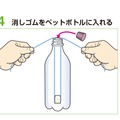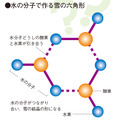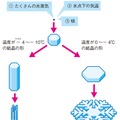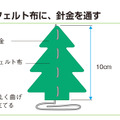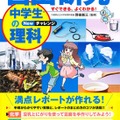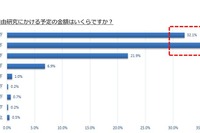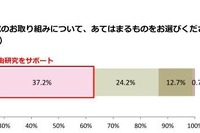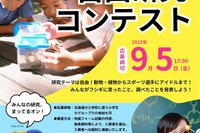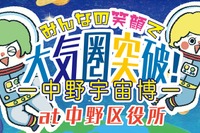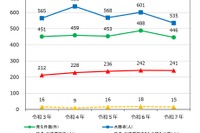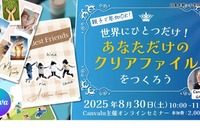ここでは、家庭ですぐに実験できる「雪の結晶を作る」方法をご紹介。自由研究テーマ選定の参考にしていただきたい。
自由研究:中学生向け 小学生向け
雪の結晶のできかたのしくみを知る~雪の結晶を作ってみよう~
第2分野【地学】実験・観察
制作時間:1時間 難易度:★★★
雪は、どうやってできるのでしょう。この実験では、「平松式人工雪発生装置」を使って、ペットボトルの中に雪のもととなる結晶を作ってみましょう。
用意するもの
ゴムせん(6号サイズ) 500mLのペットボトル つり糸(約60cm) 発泡スチロールの箱(フタがついているもの) ドライアイス*
そのほかのもの 消しゴム、軍手、ホチキスの針、カッター
*発泡スチロールの箱にいっぱい入るぐらいの量を用意しましょう。

実験1 やってみよう 雪の結晶を発生させる
★手順 全6工程
雪の結晶は、さまざまな気象条件がかさなってできます。
この実験では、雪のできる条件を人工的に再現して、雪の結晶を作ります。
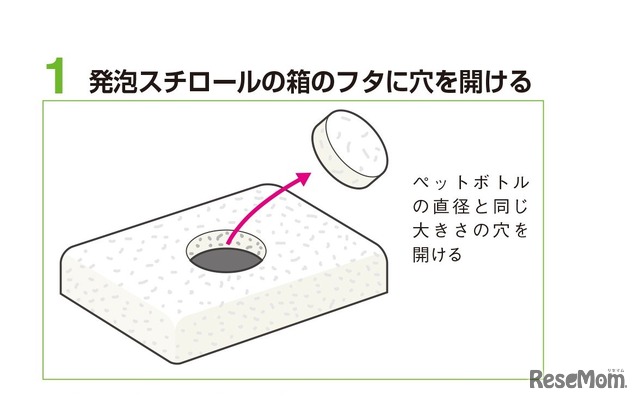
フタの中央にカッターで穴を開ける。
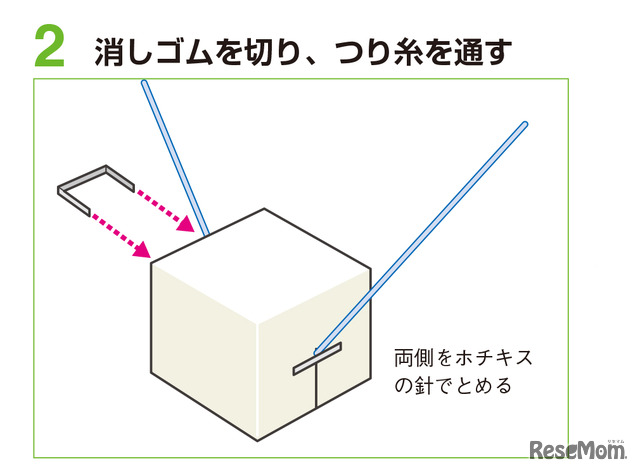
ペットボトルに入る大きさに切った消しゴムに、カッターで切りこみを入れて、つり糸を通す。切りこみの端の少し下で、つり糸をホチキスの針でとめる。

ペットボトルに水を入れてよく振り、そのあとに水を捨てる。次に10回ほど息を吹きこむ。
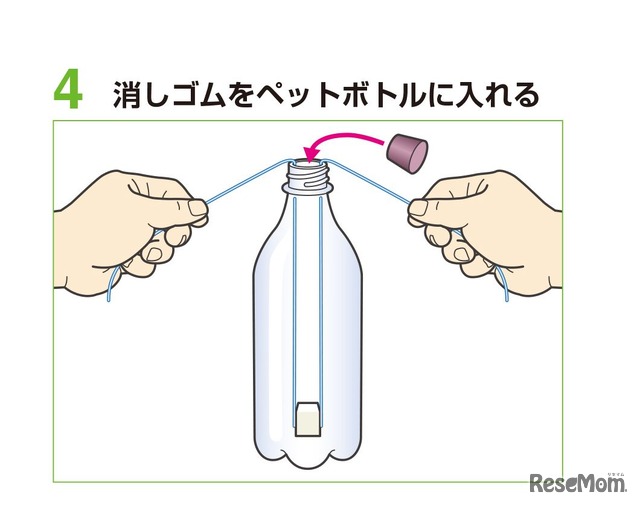
つり糸をつけた消しゴムをペットボトルの中に入れて底につけ、つり糸がピンと平行にはった状態にしてゴムせんをする。
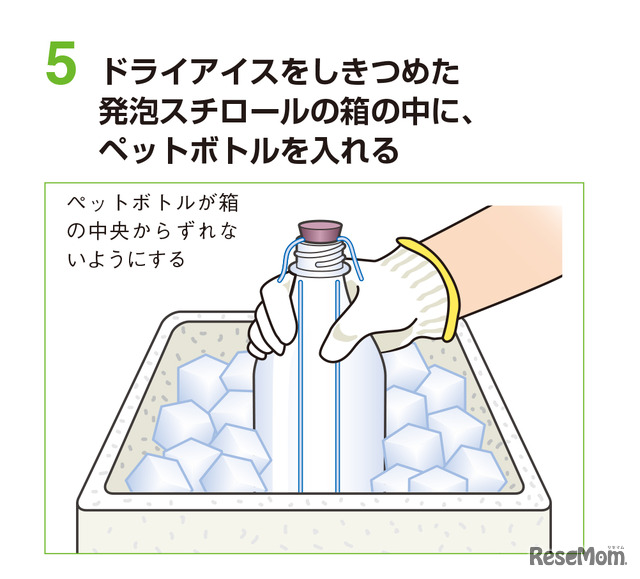
ペットボトルを箱の中央に入れる。そのまわりに砕くだいたドライアイスをしきつめて、フタをする。
※軍手を使います。部屋を換気できるところで実験しましょう。
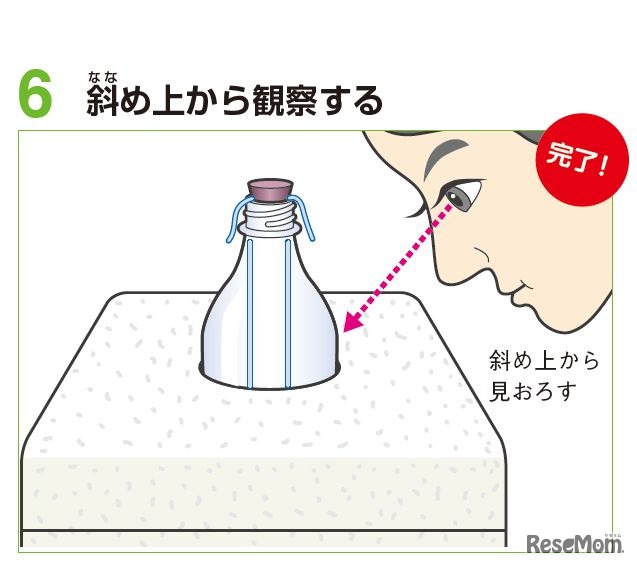
うまくいかないときには
ペットボトルをよく振る
●ペットボトルの内側全体が水にぬれるように、よく振りましょう。
●ペットボトルがよく冷えるように、ドライアイスは箱いっぱいに入れましょう。
●ペットボトル内の糸がたるまないように、左右の長さを調節しながら消しゴムを入れましょう。
なぜそうなるの? ~雪の結晶ができるしくみ~
水蒸気が氷点下で核となるものと結びつき、雪ができる
雪は、上空で空気中の水蒸気が凍ってできる結晶です。結晶の核は約1000分の1mmの細かいちりで、これに水蒸気が凍りつくとやがて雪の結晶になるのです。
温度や湿度などの条件によって、雪の結晶はさまざまな形になりますが、結晶ができるときに必要な条件は、(1)たくさんの水蒸気、(2)低い気温、(3)核になる細かい物質の3つです。
実験1では、まずペットボトルの内側を水でぬらしてから、息を吹ふきこみました。これは、内側を水蒸気で満たすためです。さらに、ドライアイスを使って気温を氷点下にすることで、細いつり糸が結晶核の代わりをしています。
ペットボトルを入れてから数分後には、糸に白く霜しものようなものがつき始めます。15~20分後には、針状の結晶が成長していくようすを見ることができます。
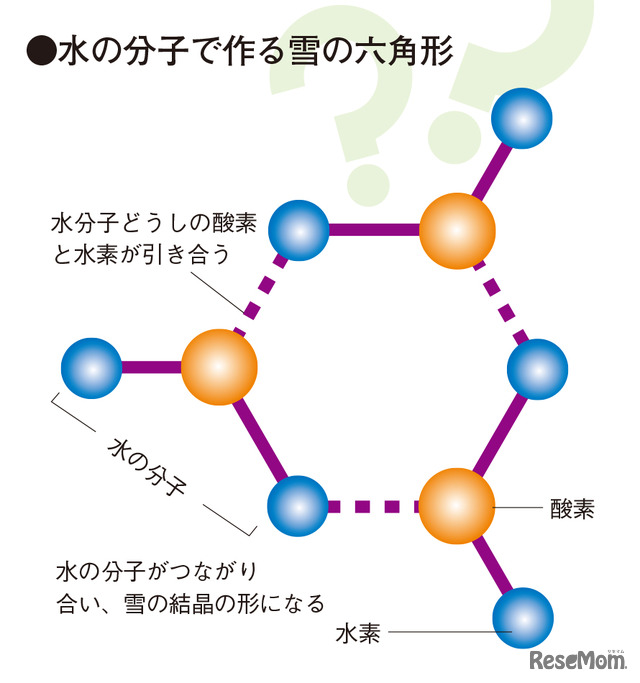
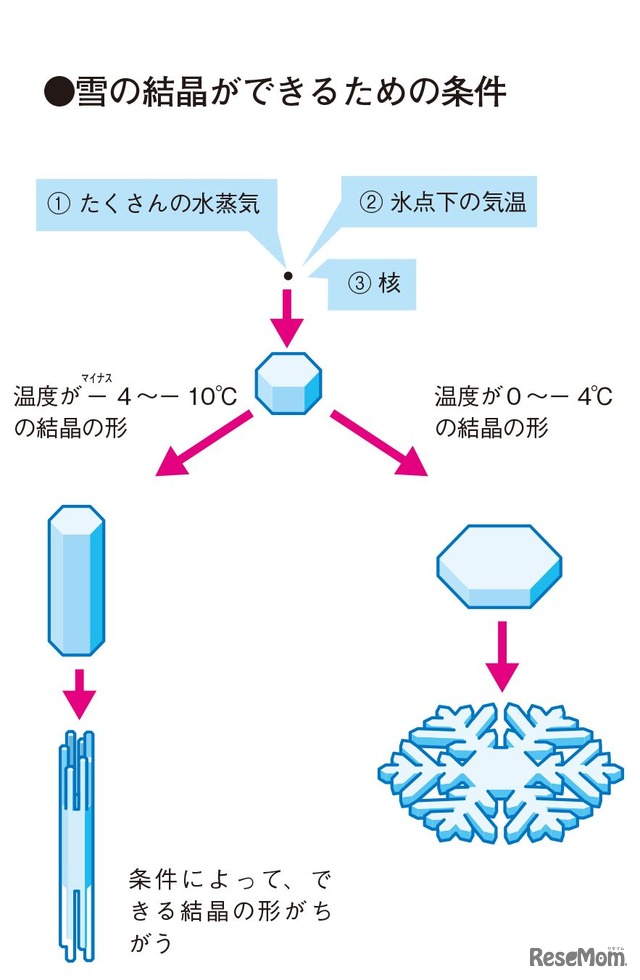
実験2 やってみよう 常温の部屋で雪のような結晶を作る
★手順 全4工程
次はドライアイスを使わずに、常温の部屋で雪の結晶のようなものを作ってみましょう。この実験では、アクリル樹脂用の接着剤が気化熱(※)によって温度を下げるしくみを利用します。
※物質が液体から気体になるとき(これを「気化」という)、近くのものから吸収する熱のこと。
用意するもの
フェルト布、針金、ペットボトルのフタ、アクリル樹脂用接着剤(二塩化メチレン入り)
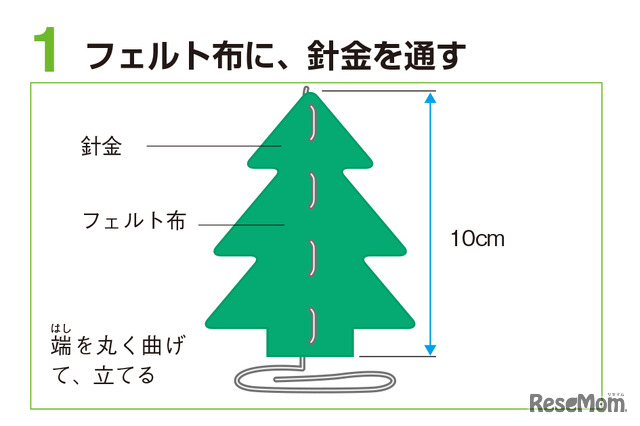
木の形に切りぬいたフェルト布に、針金を通して立たせる。木の高さは約10cmくらいにする。
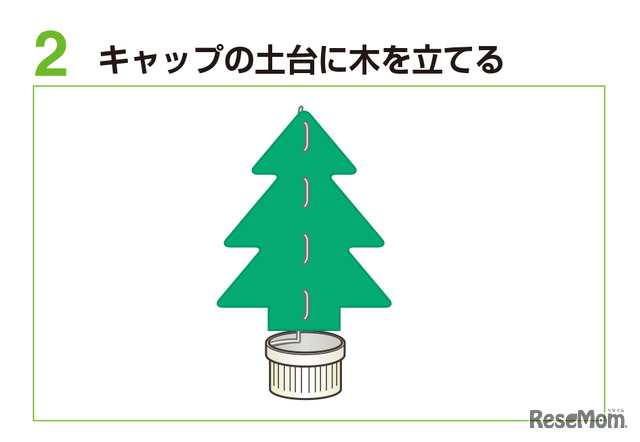
ペットボトルのキャップに、1 で作った木を立てる。
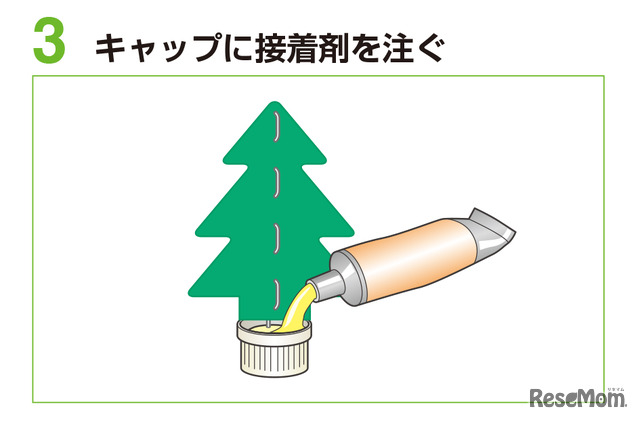
フタにアクリル樹脂用接着剤を静かに注ぎ、フェルトの下の部分がひたるようにする。
※換気できる部屋で実験をしましょう。

接着剤が気化するときに周囲から熱をうばう。このため、フェルト布の先が0度以下になると、フェルト布の繊維を核とした、白い結晶ができる。
レポートのまとめかた
実験1では、ペットボトルをセットした時刻、時間ごとの雪の結晶の形や大きさ、成長のしかたなどを記録して、写真やビデオに撮っておきましょう。
実験1では、箱につめるドライアイスの量や、ペットボトルに吹きこむ息の量を変えた場合、雪の結晶はどのようになるのか、温度の変化と合わせて観察してまとめましょう。

発行:永岡書店
<著者プロフィール:野田 新三(のだ しんぞう)>
1970年大阪生まれ。不思議に思ったことは「自分で確かめたい」という気持ちから、理科に興味を持つ。95年千葉大学大学院教育学研究科を修了後、理科の教諭として教壇に立つ。