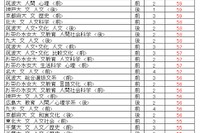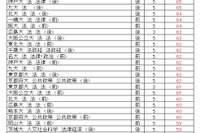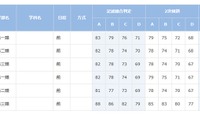ポプラ社の協力のもと、リセマムでは、読者限定で本書の一部を無料で公開する。予定調和では終わらない、ときに残酷でリアルな、4つの家庭の「中学受験」の行方はいかに…。
前回のお話はこちら。第二章 真下つむぎ(五月) 3-2
塾の授業もあまり集中できなかった。こんな日にかぎって漢字の猛特訓があり、いつもより長引いた。
「マッツンって、訛ってるじゃん。しちょる、って言ったりするから、東北? 九州? とかって思ってて訊いたらさ、東京出身だった。しかも、六本木ヒルズの近くだって」
伽凛が話しているマッツンというのは、算数の松野先生のことだ。
塾は駅に近いから、一緒に歩ける距離は短いけれど、自由におしゃべりできるこのひと時がつむぎは好きだった。それなのに、今日はうまく笑えない。夜が終わると、朝が来る。また学校だ。たぶん今朝以上に気が重くなりそうで、すでにどんよりした気分になる。
東急大井町線の大岡山駅まで帰る比呂が抜けて、北口へ向かった。つぎに唯奈はお父さんが車で待っているようで、駅とは反対方向に曲がっていく。
南口から大井町線で尾山台駅まで一人で帰る伽凛。涼真は東横線学芸大学駅らしいが、いつも駅前のカフェでお父さんが待っていて一緒に帰ることになっていた。
「なんか、今日つむぎ元気なくない? 」
三人になった時、伽凛が訊いてきた。
「僕も思った。なんかあったの?」
涼真も言う。
「そんなことないよ」
急に矛先を向けられ、とっさに明るくしようとした声が不自然に裏返ってしまう。心配してくれる二人の顔を見たら、話を聞いてもらいたい気持ちが湧き上がってきた。でも、もう駅についてしまう。それに話し出したら、きっと止まらなくなりそう。なによりも、早く帰って寝たかった。
「まあ、何もないならいいけど。じゃあねー」
南口の改札に向かって伽凛は手を振りながら歩いていく。
「それじゃあ」
涼真もお父さんと待ち合わせているカフェに向かっていった。
二人が羨ましい。
伽凛はきっと、学校でもたくさん友達がいるに違いない。私立の小学校に通っている涼真も、いつだったか学校は楽しいと言っていた。
踏切を渡ってロータリーを通り過ぎると、同い年くらいの子供たちの姿が見えた。東フロの校舎から出てくる。そうだ、今日は漢字の特訓でいつもよりも長引いたので、東フロの終わる時間にぶつかってしまったのか。知っている子に会いたくない。誰よりも会いたくない子がいる。駆け足で駅前から遠ざかっていくと、誰よりも会いたくない顔が目に飛び込んできた。向こうもこちらに気付いて、目を見開いた。無視して通り過ぎよう。
「つむぎも一人で帰る派なんだー」