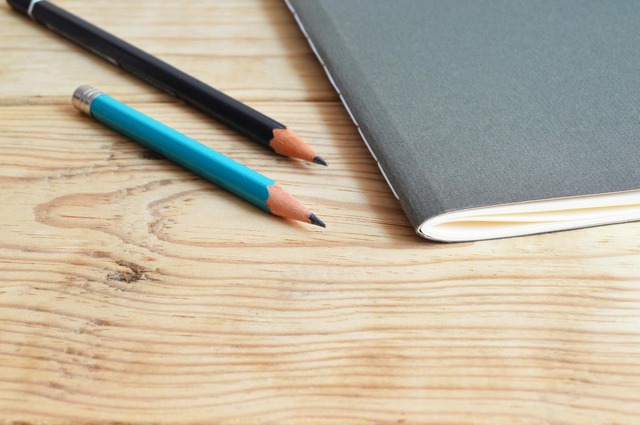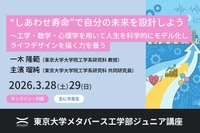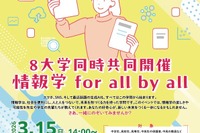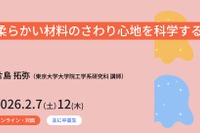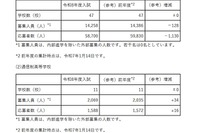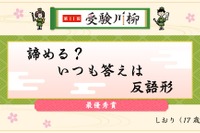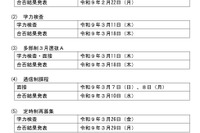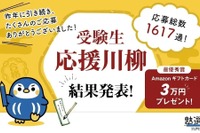東大に合格するような子供が育つ家庭では、親のさまざまな工夫が行われている場合が多い。勉強面・生活面・コミュニケーションの面などさまざまな面から、他の家庭とは少し異なることが行われている。
本記事ではその中で、「テストに対して親はどんな対応をしていたのか」について共有したい。東大に合格した受験生たちにも、テストでうまくいかなかった経験がある。そんなとき、東大生の親はどのように対応していたのか。100人アンケートの結果から見えてきたことを共有する。
目標点数を紙に書く
まず、小学生~中学生の間は、きちんと目標点数を書かせた紙を提出していたという家庭が多かった。
・各科目の目標点数を書いた紙を提出して、その点数が取れていれば勉強について一切口出しはされなかった。逆に取れていないと指摘されたので、指摘されないように頑張った。
・「平均点+10点」と目標点を決めて、そのために頑張る習慣を付けていた。しっかり各科目で設定して、何個目標点を達成できたかでご褒美をもらえた。
このように、目標点を具体的に作っている場合が多かった。この目標点作りは、子供と親で一緒にやっている場合もあれば、子供から提出されるのを待っているだけという家庭もあった。そしてそれに応じてご褒美をあげたり、逆に注意したりということをしていたようだ。
アンケートの結果から分かったことは、テストの結果に対して親がやってはいけないのは、「なんとなくぼんやり」で子供に指摘してしまうことだ。
たとえば「算数が60点って、なんだか低い気がする」と思って「もっと算数がんばりなさい」と言ってしまったとする。このとき、子供としては、「苦手な科目で、この前が50点だったから10点も上げたのに、認めてもらえなかった」と感じてしまうかもしれない。
ところが東大生の親は、テストの点数に対して、子供と建設的な対話をしようと意図していそうだ。目標点を作ることで、感情的になったりせず、子供に対してしっかりと「あと●点取るためにはどんなことをしたらいいかな?」といった声かけをしているのだ。
「今、やろうと思ってたのに」の親子バトルを避けるには
子供にとっても、目標を明確にすることには大きな意味がある。そもそも、「テストで良い点を取りたい」という生徒は多いだろうが、明確な基準がない場合が多い。
そこで、「次のテストで算数は70点、社会は80点を取りたい」などと、「良い点」を具体的にして明確な目標設定をする。こうすることで、目標をクリアした時には「うまくいった!」と喜べ、クリアできなかった時には「自分の努力が足りなかった」と反省することができる。漠然と「良い点を取りたい」と思っているだけだとこうはいかないだろう。
親と子供のコミュニケーションのうえでも、この方法は有効だ。自分の子供がきちんと勉強しているのか、勉強に対して指摘する基準ができるからだ。
もし勉強していない時間があったとして、そこで「もっと勉強しなさい」と言っても「今やろうと思っていたのに」「さっきまでやってたんだよ」という親子喧嘩になりかねない。これが行き過ぎると、子供も、親が見ているタイミングだけ勉強するようになってしまう。だからこそ、きちんと目標点数を書いた紙を親子で共有し、勉強に対して指摘する基準を設けておくことが有効なのである。
もうひとつ重要なのは、絶対評価の点数で考えるのではなく、差分で子供を評価することだ。たとえ50点だったとしても、30点が50点になったのであれば20点もアップしたことになる。努力をしっかり褒めてあげられるように、「今回のテストの結果から次回はどれくらいアップさせるのか」という目標を一緒に作ってあげるべきだと言える。
反抗期に有効な方法とは
一方で、中学生から高校生になると反抗期を迎える。となると、「目標点数を書きなさい」と親が言ったところで、反発されたり、「言われたから勉強する」というのが常態化して自分から勉強しない子になったりするのが、この時期の子供を抱える親の大きな悩みだろう。しかし、小学生の頃以上に学校での定期テストは重要になってくる。では、定期テスト前にはどのように対応していたのだろうか。
東大生の親は、基本的に勉強に対して口出しをせず、もし勉強をしていないと感じた時には、「勉強、大丈夫?」という形で声をかけることが多いようだ。叱ったり注意したりするのではなく、日常会話として聞く。勉強していないという姿を見て、その理由や事情などを何も聞かずに頭ごなしに勉強を促すのではなく、勉強しない理由をしっかりと理解しようとして質問をする、ということだ。
なぜこれが有効なのか。
たとえば子供に対して、手を洗ってうがいをしているかどうか、親御さんは確認することが多いだろう。「外から帰ってきたけど、手は洗った?」と。意図として「洗わなかったら風邪をひいてしまったりして大変だよ」ということを心配して聞いているので、大きな反発はないだろう。それと同じくらいのテンションで、「勉強、大丈夫?」と聞く家庭が東大には多い。
・「勉強しなくていいの?」と聞かれた。正当な理由があればそれ以上に追求はしてこなかった。
・勉強しなさいとはたぶん言われたことがない。中学生の時に、定期テスト直前なのに全然勉強していない時は、「大丈夫?」と聞かれたが、それ以外はなかった。
ただ、保護者が普段の会話の中で、勉強についてさらっと尋ねる。こういう声がけだと、勉強に対するやる気を削ぐことがなくなるようだ。
定期テスト前だからといって、毎日コツコツと勉強しているから、特段慌てて勉強する必要はないという子もいるだろう。もちろんそんなケースは少ないのかもしれないが、しかし子供には子供なりに何らかの考えをもっている場合だってある。それこそ本当に、「今やろうと思っていた」のかもしれない。そういう場合も考慮し、ただ「勉強、大丈夫?」と聞くのがいいのである。
具体的な目標を共有したり、さりげない声かけをしてみたり、子供との関係性に合わせて試してみてほしい。
カルペ・ディエム所属の東大生講師に相談してみる