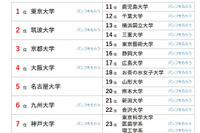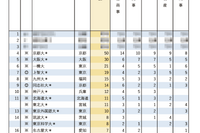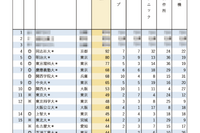---
大学関係者にとって「2018年問題」といえば、まず頭をよぎるのは、この年から大学に進学する18歳人口が大幅に減少に転じ、それによって大学間の学生獲得競争が激化して、倒産に追い込まれる大学も出てくることが予想される問題のことでしょう。この問題は、読売新聞が2017年12月31日の朝刊でも報じたように、日本の大学教育が抱える問題として多くのメディアが報じている教育課題のひとつです。
今日取り上げるのは、こちらの2018年問題ではなく、もうひとつの2018年問題です。それは、大学教職員の雇用に関わるものです。
ふたつの2018年問題は、深いところで関わりを持っているのですが、18歳人口の減少に関わる2018年問題は、これまでにも多く議論されてきたところですので、ここでは大学教職員の雇用に関する2018年問題に的を絞ることにしましょう。
◆2018年問題って何?
1、問題の背景
・労働契約法って何?
・なぜ改正したの?
・改正の内容は?
2、労働契約法の改正は大学にどう影響するの?
・5年ルールが適用されたら
・話題の「2018年問題」実際に起こっていること
・今後はどうなる?東北大学・東京大学を例に
3、次は「2019年問題」がやってくる
・進む「働き方改革」
・大学が抱える最大の課題
4、大学が生き残るために
1、問題の背景
・労働契約法って何?
・なぜ改正したの?
・改正の内容は?
2、労働契約法の改正は大学にどう影響するの?
・5年ルールが適用されたら
・話題の「2018年問題」実際に起こっていること
・今後はどうなる?東北大学・東京大学を例に
3、次は「2019年問題」がやってくる
・進む「働き方改革」
・大学が抱える最大の課題
4、大学が生き残るために
1、問題の背景は? ―労働契約法の改正―
2018年問題を理解するには、今から約5年前の2013年の労働契約法の改正について知らなければなりません。労働契約法自身も、2009年に成立した比較的新しい労働法分野の法律です。そこで、10年前に立ち返って、この法律の成り立ちをみたうえで、2013年の改正に触れましょう。
(a)労働契約法ってなに? ―雇用分野のヌーヴェルヴァーグ―
よく知られているように、労働者が働くにあたって最低基準を定めた法律としては、労働基準法(1947年制定)がありますが、労働契約に関する民事的なルールについて体系的に定めた法律はありませんでした。その結果、労働者と使用者との間で争いが生じたときは、裁判所の判決が蓄積されてできあがったルールとしての「判例法理」を当てはめて解決するという行き方が一般的でした。しかし、判例法理は、労働者と使用者双方にそれほど知られたものではありませんでした。
そこで、労働関係を安定的なものとするため、労働契約の基本的な理念や共通する原則、これまでに確立した判例法理をひとつの体系としてまとめることでできあがったのが、労働契約法なのです(2008年3月施行)。
この法律が必要とされたのは、雇用形態が多様化したことや、年棒制などの成果主義的な人事制度や人事考課の導入によって、これまでは労働協約(※1)や就業規則で一律的・画一的に決められていた労働条件ではなく、個人的に異なる労働条件を定める必要性が出てきたことによります。
この法律は第1条で「合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資するること」を目的とすると述べています。
わずか19か条しかなかったのですが、わが国ではじめて制定された労働契約に関する法律です。雇用分野のヌーヴェルヴァーグ(新世代を切り開く波)のようなものだと私は思っています。
そのすべてを説明することはできませんので、ここではあと後で述べる改正に結びつく有期労働契約(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託などの呼び方にかかわらず、半年や1年など期間の定めのある労働契約のことです)に関するものについて触れておきましょう。なお、労働契約法は、労働基準法とは異なり、使用者と労働者の間の民事上の契約ルールを定めたもので、罰則規定はありません。
労働契約法は、有期労働契約の締結、更新そして雇い止めに関する基準として、使用者に4つのことを課しました。契約期間満了後の更新の有無を明示すること、3回以上更新された契約や1年を越えて継続勤務している労働者の契約を更新しない場合には契約期間満了の30日前までに雇い止めの予告をすること、労働者の求めがある場合雇い止めの理由を明示すること、そして契約更新の場合できるだけ更新期間を長くするよう配慮することです。また、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の満了まで労働者を解雇することができないこと(17条1項)、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮すること(同条2項)も規定されました。
(b)なぜ改正したの?
有期労働契約で働く人は、全国で約1,200万人と推計されています。そしてその3割が、通算5年を越えて有期労働契約を反復・更新している実態があります。有期労働契約で働く人は常に、契約を更新されず雇い止めになる不安を抱いています。また、有期労働であることを理由として、正社員と比べて不合理な労働条件で働いている場合も多く見受けられます。
2008年の労働契約法は、雇用のヌーヴェルヴァーグではあったのですが、有期労働契約の雇い止めにはそれ程効果を示すものではありませんでした。すでで触れたように、雇い止めの予告、理由の明示、再更新における雇用期間の長期化の配慮に留まるもので、使用者による自由な雇止めを前提としていたからです。
こうした問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現していこうという趣旨から、改正が求められることになったのです。もちろんその基底には、少子高齢社会における安定的な労働力の確保を図ろうという政策的判断もあります。
(c)改正の内容って? ―雇用分野のラドマレ―
今回の改正では、有期労働契約について、次の3つの重要なルールが定められることになりました。私は、この改正労働契約法を、雇用分野のラドマレ(激動をもたらす大波)と呼んでいます。

画像:労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)(画像出典:厚生労働省)
(i)有期労働契約から、無期労働契約への転換(18条)
有期労働契約が反復更新されて通算で5年を超えたときは、労働者からの申込みにより、期間の定めのない無期労働契約へと転換できるルールが規定されました。ここではこれを「5年ルール」と呼んでおきましょう。ただし、無期転換しても、賃金や労働時間などの労働条件は、有期労働契約の時と同じなことに注目しておいてください。
(ii)「雇止め法理」の法定(19条)
最高裁判所の判例(※2)で確立していた「雇止め法理」が、そのままの内容で法律の規定となりました。この「雇止め法理」とは、使用者の解雇権濫用の法理を「類推適用」したもので、実質的に無期契約と変わらない状態にあったり、雇用が継続されることへの期待がある場合には、使用者による雇い止めを認めないというものです。使用者による雇い止めは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」と認められない限り、適法とはされなくなったのです。
(iii)不合理な労働条件の禁止(20条)
有期の労働者と無期の労働者との間で、期間の定めがあることによって労働条件の不合理な相違を設けることが禁止されました。通勤手当や食堂の利用、安全管理に関わる相違は、不合理とされたのです。
(d)なぜ「2018年問題」といわれるの?
(c)で説明した(ii)は、2012年8月10日の公布日と同じ日に施行されましたが、(i)と(iii)は、2013年4月1日からの施行となりました。
もうおわかりかと思いますが、(i)の通算契約期間のカウントは施行日以後に開始する有期契約が対象となりますので、「5年ルール」の最初の適用が問題となってくるのが2018年なのです。「2018年問題」といわれるのはここからきています。
では、2018年問題について、企業や大学の、職員を利用する側はどのような対応をするのでしょうか?
労働契約法の改正は大学にどのような影響を与えるの?
2018年問題について、企業や大学の使用者は、雇用者に対してどのように対応するかというと、基本的にふたつあります。進んで有期契約から無期契約へと転換していくか、それとも「5年ルール」を回避するために更新期間を5年未満とする有期契約を結ぶかです。企業のなかには、人材確保のために積極的に無期契約への移行を図る方針を打ち出したところもあります。
では、大学はどのように対応するのでしょうか。
(a)「5年ルール」が大学に適用されると…
過去のテレビドラマで、大学病院内は「白い巨塔」とも揶揄されたように、大学の内情はなかなか外からは見えにくいものです。誰が教員で、職員で、はては有期契約の教授かどうかなどは、一見してわかりづらいでしょう。
教授や准教授にも任期付きもいますし、任期付きが普通の雇用形態となる助教や助手、TA(ティーチングアシスタント)もいますし、特定のプロジェクトのため任期付きで民間企業などから派遣されてきた研究者、そして何よりも非常勤講師もいます。それに、教育職だけで組織は回らない以上、事務職もいて、そのなかには、いわゆる契約職員もいます。
雇用形態の違いがあるとしても、大学教授であれ、助教やTAであれ、契約職員であれ、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる」労働者で、大学は「使用する労働者に対して賃金を支払う」使用者です(労働契約法2条)。両者には労働契約法が適用されます。
ということは、先にあげた「5年ルール」も適用される結果、たとえば、ある大学で非常勤講師を5年続けると、6年目からは、「申込み」すると常勤になれるということです。1年契約が通常の非常勤講師にとっては、雇用の安定というメリットがあり、まさにそのことは労働契約法の目的にかなうものともいえます。
他方で、使用者である大学側からは別な見方もできます。特にふたつの問題点が指摘されるでしょう。
ひとつは、若手研究者の育成やキャリアパスに関わるものです。助教や助手など育成途上の研究者は、有期雇用のポストを一定期間経験し、業績を積んだうえで任期のない無期のポストに就くのが標準的なシステムです。これは、テニュアトラック制度といわれるものです。通常、5年程度が有期雇用期間として設定されます。こうしたポストに就く研究者を任用から5年後ただちに無期労働契約に転換することはほとんど不可能ですので、雇用期間を5年未満にするしかなくなります。これでは逆に十分な研究時間が確保されませんし、厳正な業績評価もできないことになる結果、若手研究者のキャリアパスが中断されることにもなりかねません。
もうひとつは、非常勤講師、とりわけどこかの大学で正規雇用されず、複数の大学をかけ持ちする専業的な非常勤講師の問題です。大学は、学生や社会のニーズの変化に迅速・柔軟に対応し、また経費を節減するため、多くの非常勤講師を雇い入れています。非常勤講師の契約期間は通常1年で、必要とされれば更新されます。非常勤講師の雇用は、大学にとっての調整弁的な働きをしているともいえます。こうした非常勤講師に「5年ルール」が適用され、無期契約への転換を余儀なくされるとなると、大学側は躊躇せざるを得なくなり、5年を上限とする雇用契約しか結ばないということになるでしょう。事実、雇用契約法が施行された2013年に、非常勤講師の契約期間の上限を5年とする就業規則の改正を行った大学がありました。これでは、雇用の安定という点ではマイナスの効果をもたらしてしまいます。
(b)実際に起こっている問題
こうしたふたつ問題に対する危惧から、国公私の設置形態を問わず大学団体から要請を受けたこともあり、政府は、特例措置を設けました。研究開発力強化法と大学教員任期法の一部改正です(2013年4月1日施行)。前者は、有期雇用の研究者に、後者は、有期雇用の教員に適用されます。大学の教育職・研究職に携わるものに対しては、先の「5年ルール」が10年に引き伸ばされたのです(これを「10年延長ルール」と呼んでおきましょう)。
私の勤務する大阪府立大学でも、この任期法等の改正を受けて、平成28年12月非常勤講師に関する規程に、契約期間の更新は10年を超えないものとする規定が置かれました。
この特例措置によって、「2018年問題」は、ひとまず回避されたといえなくはありません。大学は、若手研究者や非常勤講師など有期雇用の教員を今後さらに5年をかけて、無期雇用を見据えた「品定め」ができるようになったからです。
ということは、大学にとっての「2018年問題」とは、とりあえず有期雇用職員への対応問題ということなります。
(d)今後起こりうる問題とは? 東北大学と東京大学の例
実際、東北大学では、非正規職員の有期雇用契約を5年を越えて更新できないように就業規則を改め、現在非正規で働く職員を対象にした無期雇用の正規職員への転換をはかる採用試験を実施し、応募した821人のうち、合格者は690名で、不合格となった131名は来年3月末には雇止めになる可能性が高いと労働組合が述べている報道があります(朝日新聞2017年11月29日)。
これでは、雇用の安定を目指した2013年の改正労働契約法の趣旨・目的に反します。この改正によって、「雇止め」法理が法定されたことを思い出してください。雇止めは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」と認められない限り違法となります。今後は、この労働契約法19条をめぐって、裁判所や労働委員会で争われる機会も増えそうです。大学側は、こうした司法リスクにも備えなければならなくなるでしょう。
つい最近、東京大学は「5年ルール」を定めていた就業規則を撤廃しました(産経新聞2017年12月15日)。東大は、労働契約法が改正された際に、5年以上雇用を継続する場合は、最低6か月の「クーリング(雇用中断)期間」を置くよう改定していました。6か月以上のクーリング期間をおくと、これまでの通算雇用期間すべてが帳消しとなる制度を逆手に取ったものでした。さすがに文科省が調査し、雇用の安定という改正労働契約法の趣旨に沿うよう「慎重な対応」を要請したことを受けて、継続雇用に道を開く規定に改めたのでした。今後、東大の対応が、ほか大学にどこまで波及していくか目が離せないところです。
さて、それでは、「2018年問題」は特例措置のおかげで、有期雇用の研究者や教員には無縁なものとなったのでしょうか。
2019年、労働契約法界の巨大波がやってくる
大学は、2018年問題を回避し、2023年までの猶予を与えられたのでしょうか。私は、2020年の東京オリンピックイヤー前に、労働契約法界の巨大「ツナミ」がやってくると予測しています。
(a)進む「働き方改革」、迫る施行日
そのツナミとは、安倍内閣の目玉政策のひとつである「働き方改革」、とりわけ「同一労働同一賃金」の実現に向けた法制度とガイドラインの整備です。「働き方改革」を労働生産性を改善するための最良の手段と位置づけ、賃金の上昇と需要の拡大を通じて「成長と分配の好循環」を構築し、日本経済の潜在的成長力の底上げをはかろうとするものです(働き方改革実行計画 2017年3月28日決定)。
実行計画は、働く改革の意義について、「正規」「非正規」というふたつの働き方の不合理な処遇の差は、正当な処遇がなされていないという気持ちを「非正規」労働者に起こさせ(不合理な処遇の差)、がんばろうという意欲をなくす。これに対し、正規と非正規の理由なき格差を埋めていけば、自分の能力を評価されているという納得感が生じる。納得感は労働者が働くモチベーションを誘引するインセンティブとして重要であり、それによって労働生産性が向上していく、としています。
こうした考え方を具体化するためにガイドライン案が定められました。これは、正規か非正規かという雇用形態にかかわらない「均等・均衡待遇」を確保し、同一労働同一賃金の実現を目指すものです。その対象は広く、賃金全般(基本給、昇給、ボーナス、各種手当など)だけでなく、教育訓練や福利厚生にまで及びます。
基本給を例にとってみましょう。基本給は、職務、職業能力、勤続年数に応じて支払われるなど趣旨・性質はさまざまですが、ガイドライン案はそれぞれの趣旨・性質に照らして、実態に違いがなければ同一の(均等)、違いがあれば違いに応じた支給(均衡)を求めているのです。
よく賃金の差を正当化するために、「正規と非正規とでは将来の役割期待が異なるから、賃金の決定基準やルールが異なるのだ」と説明されてきましたが、こうした主観的・抽象的な説明では足りず、職務内容や職務内容・配置の変更範囲、その他事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理なものであってはならないとされるのです。
そして、このガイドライン案をもとに法改正がおこなわれ、改正法の施行日に施行するものとされています。その施行日が2019年にくるのです。この法改正は、不合理な待遇差の是正を求める労働者が裁判で争える根拠を提供するものであるとも述べています。
2018年に無期雇用に転換する者には、とりあえずこの改革は適用されません。すでに述べたように、これまでの労働条件が引き継がれるからです。しかし、2019年以降は、同一労働同一賃金の趣旨を読み取った手直しをすることが求められるでしょうし、「10年延長ルール」が適用される2023年にはまさに均等・均衡待遇による同一労働同一賃金を前提とした就業規則が求められるでしょう。これまでのように非正規教職員を調整弁的に取り扱うことはできなくなります。
(b)大学が抱える最大の課題
では、大学がこの労働契約法界のツナミに対応するための最大の課題とは何でしょうか。もうおわかりでしょうが、賃金原資、つまり大学のお財布にかかわるものです。
これが企業ならば、生産性の向上、内部留保の切り崩し、価格転嫁、あるいはサービス低下などで原資を確保することになるでしょうが、大学ではなかなかそうはいきません。「入るを図る」ために運営費交付金の増額を求めたり(国公立大学の場合)、授業料をアップしたり(私立大学の場合)することはほとんど望めませんし、とり崩せる大きな基金のある大学はそう多くはありません。また、教育の質を維持するためにはサービスを低下させることもできません。残るは「出る制する」ために、高い人件費割合を下げるくらいでしょうか…。
同一労働同一賃金によって正規と非正規の待遇格差・賃金格差の壁がなくなくなることは、何をもたらすのでしょうか。私には、これは無期雇用(正規雇用)の教職員の現行の処遇システムに大きな変化・変更をもたらす要因となるようにみえます。
より具体的にいうと、(1)有期雇用が中心的雇用形態となる、(2)賃金体系が業績主義となる、というものです。
(1)は、有期雇用から無期雇用への転換という改正労働契約法の趣旨からみると逆説的なようにみえますが、待遇・処遇における有期・無期の区別の必要がなくなると、大学側としては無期で雇用する必要性がなくなる、とでも言えるでしょうか。「三無主義的教員」、つまり“学位無し、業績無し、やる気無し”教員を終身雇用するリスクから解放されることを意味するからです。(2)は働きに応じた処遇、つまり大学教員が担う研究、教育あるいは社会貢献というアウトプットに寄与・貢献のあったものを正当に評価することからくることです。
(1)と(2)は相反的なものではありません。とすると大学教授が、野球選手のように「年棒制・複数年契約」で働く日もそう遠くはなさそうです。
大学が生き残るための“備え”
大学は現在、「内憂外患」に直面しています。内憂とは、もうひとつの「2018年問題」―18歳人口の大幅な減少による学生獲得競争に勝ち抜き、あわせて全入時代において「教育の質」の保証をはかるための大学間競争―であり、外患とは、「グローバル化」―社会や産業のグルーバル化に対応して、広く世界から優秀な学生、教員、研究者を集めるという大学間競争―です。ふたつの問題に挟まれ、難しい舵取りを求められています。まるで、ギリシャ神話にでてくるスキュラとカリュブディスの狭間を通り抜けなければならないオデュッセウス、とでもいうところです。
これらの課題に取り組むためには、正規雇用の教員だけでは無理です(もちろん、正規雇用の職員だけでも不十分です)。かといって、加速化する学生・社会のニーズの変化と大幅な増収の見込めない大学財政からして、すべての非常勤講師を正規化することはできません。
となると、行われるのはやはり「選別」しかなくなります。有期雇用の大学職員が対象となる2018年問題は、同じく有期雇用の大学教員にとって5年後の“殷鑑(いんかん)”となるように思えてなりません。
2018年問題は“ひとまず”回避されました。しかし、労働契約法界における「2019年のツナミ」は、本来の自然災害のような予測不可能なものではなく、必ずやってくるものです。生き残りを目指す大学ならば、これを自覚し、備えなければなりません。残された時間はそう多くはないのです。
※1 労働契約に似たものとして、労働協約があります。これは、労働組合が使用者との間で結んだ取り決めのことで、集団的な労働関係に関わるものです。
※2 東芝柳町工場事件最高裁1974年7月22日判決;日立メディコ事件最高裁 1986年12月4日判決参照
---
労働契約法の詳しい趣旨や内容については、厚生労働省のパンフレットが詳しく解説している。水鳥教授は、今後行われる「働き方改革」に関連する諸法律の改正についても留意してほしいとしている。
 水鳥 能伸(みずとり よしのぶ)
水鳥 能伸(みずとり よしのぶ)大阪府立大学経済学研究科教授。同副研究科長。専攻長、社会科学系長も兼務。高等教育開発センター員。専門は憲法、人権法、フランス公法。フランスの提携大学等との国際交流にも携わる。著書に「亡命と家族 - 戦後フランスにおける外国人法の展開」(有信堂、2015年)、「謎解き日本国憲法(第2版)」(同、2016年)その他。













![転職を決めた本当の理由とは…Teacher’s[Shift]](/imgs/std_m/392873.jpg)