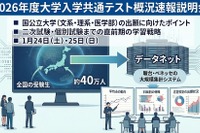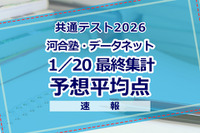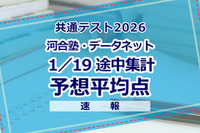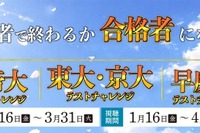毎年、多数の東大合格者を輩出している駿台予備学校。駿台といえば伝統あるお茶の水校、医学部専門の市谷校が象徴的だが、全国には比較的小規模で講師と生徒の距離が近く、アットホームな雰囲気の校舎も多い。
今回取材に応じてくれたのは、その中のひとつ、横浜校で受験生活を過ごした2人。両名ともに、公立中学校・公立高校を経て、東京大学合格を果たした大学1年生だ。幼少期の学び、公立校での生活、夏休みの過ごし方をはじめ、東大合格までの軌跡について語ってもらった。
【話を聞いた人】
山野 幸大さん:東京大学理科二類1年、神奈川県立横浜翠嵐高等学校出身
原田 莉沙さん:東京大学文科三類1年、横浜市立南高等学校出身
中学まで東大受験は考えていなかった
--いつから東大を目指そうと思いましたか。
原田さん:明確に東大を目指すことにしたのは高校2年の冬です。それまでは理系を目指していたのですが、数学に伸び悩んだこと、英語の成績が良く、国際関係論に興味があったことから、高2の冬に文転しました。その際、「大学受験は最難関を目指して努力すればうまく行くはず」と思い、第一志望を東大に決めました。残り1年で社会2科目を仕上げる必要がありましたが、幸いにも暗記が得意で、特に世界史の勉強にのめり込み、自分はやはり文系に向いているなと感じました。
山野さん:僕が東大を意識しはじめたのは中学3年のころです。そのころから通いはじめた塾で勉強が楽しくなり、「せっかくなら最高学府の東大で勉強したい」と思うようになりました。志望校だった横浜翠嵐高等学校からは、ここ数年間は毎年学年の1割以上が東大に進学していて、東大を目指す環境としてはとてもよかったと思います。

--おふたりは公立高校の出身ですが、小学生のころはどんなふうに過ごしていましたか。
原田さん:当時の習い事は、公文、ピアノ、書道、スイミングです。公文は先生の指導が熱心で、小学生の間に高校の数学レベルまで進んでいました。中学受験専門の塾には通っていなかったものの、公立中高一貫校である横浜市立南高等学校にはカナダ研修があると親から聞き、憧れを抱くようになりました。そこで公文をやめ、適性検査対策の塾に変えたのですが、中学受験への熱量は全然高くはなかったです。
山野さん:僕はサッカー、スイミング、書道を習っていました。小5からは、兄が通っていた地元の塾に通い始めたものの、小学生のころは宿題をやるくらいで特に勉強する習慣はなく、本もほとんど読んでいませんでした。放課後はとにかく友達と遊ぶのが楽しくて、毎日のように誰かの家に集まってはワイワイと賑やかに過ごしていました。親からは中学受験を勧められたこともありましたが、中学受験をする同級生がほとんどいない地域だったので、大勢の友達と同じ中学に行きたくて地元の公立に進学しました。
--おふたりとも比較的のんびりとした小学校時代だったのですね。中学に入学後はどのような毎日でしたか。
原田さん:学校生活では、入学当初は学校に馴染めず読書ばかりしていたのですが、吹奏楽部に入って気の合う友達もでき、楽しく過ごせるようになりました。コロナ禍で休校になってしまった時期は、幼少期から続けているピアノを弾いたり、YouTubeを見たり、ダイエットに励んだりもして、自分の好きなことに時間を使っていました。ただ、公文をやっていたころから日常的に勉強する習慣があったせいか、学校の成績は良かったです。
山野さん:僕は中学でバスケ部に入り、中学時代はその練習に明け暮れていました。毎日ヘトヘトに疲れ切るまでやっていたので、勉強は小5から通っていた塾の課題をやるのが精一杯でしたが、幸いその塾で英語や数学を先取りしていた分、学校の勉強で困ることはほとんどありませんでした。上位の成績がキープできていたため、中3からは塾を変え、本格的に神奈川県下ではトップクラスの進学校である横浜翠嵐を目指すことにしました。

東大受験に役立った幼少期の経験
--高校生活は、東大受験に向けて勉強三昧だったのか、それとも実生活も充実したリア充だったのか、どんな感じだったのでしょうか。
原田さん:私は高校では軽音部と料理部に入りました。軽音部では学園祭で演奏したり、料理部ではクリスマスケーキを作ったり、部活以外にも校内の合唱コンクールでピアノ伴奏をするなど、リア充派だったと思います。それでも、中学のころと同様、幼少期から日常的に勉強する習慣は続いていました。
山野さん:僕は高校でもバスケに打ち込んでいたので、中学時代に続いてリア充派でした。そんな忙しい中でも、一応毎朝学校で自習はしていたんですが、やはり練習がキツくて、正直なかなか手が回らなかったところが多かったです。
--おふたりとも、高校から駿台に通い始めたそうですね。駿台の授業をどのように活用していましたか。
原田さん:私は高1の夏に駿台の夏期講習を受け、ハイレベルな授業に刺激を受けたことが、駿台に通うきっかけになりました。高1の秋から数学を取り、高2からは英語を追加、さらに高3の途中からは東大向けの古文を追加しました。駿台は予習復習をしないと授業についていけないので、高校生活を楽しみながらもそこはしっかりやっていました。私の通っていた高校から東大に進学する人は少なく、どうしても学校の勉強だけではカバーしきれないことを駿台で教えてもらえたのはとてもありがたかったです。
学習面以外でも、現役東大生のクラスリーダーと話すことで、東大へのモチベーションが上がりました。
山野さん:僕は高1の1学期の期末テストで英語に苦戦したため、夏から英語を受講し始めました。さらに高2で数学を、高3で化学を追加しました。ただ、僕は原田さんとは真逆で、部活の忙しさにかまけて予習は前日に慌ててやったり、復習を怠ってしまったりと、自分が今、何をどこまで理解しているか、どこが足りなくて何が課題かをほとんど自覚できていませんでした。せっかく駿台の素晴らしいカリキュラムがあっても、漫然と授業に出ているだけではまったく身に付かず、活用しきれていなかったですね。
--今振り返って、小学校、中学校時代の過ごし方が東大受験に役立ったと感じるところはありますか。
原田さん:私は学習習慣です。幼少期から毎日机に向かう習慣があったことで、学校生活や自分の好きなことを満喫しながらも、毎日少しずつでも学力を伸ばしていけたように感じています。特に英語は公文のおかげか、あまり勉強しなくても得意科目で、大学受験でも武器になりました。
山野さん:僕は体力です。小学生のころは友達と校庭や公園で毎日のように走り回っていましたし、中学・高校ではバスケ部でのハードな練習で鍛えられました。東大受験は対策しなければならない量も多く、体力がなければ長時間の勉強には耐えられません。今振り返っても、幼いころからしっかり運動をし、十分な体力を付けておくことはその後の長い人生にも大いに役立つと思います。

夏休み、焦りは禁物…優先すべきは?
--まもなく夏休みです。おふたりは受験生としての夏休みをどのように過ごしていましたか。
原田さん:高3の夏には初めて東大の過去問に触れ、東大の論述問題に慣れるようにインプットとアウトプットを行ったり来たりしながら、実践力を高めていきました。そして、夏休み中に実施される東大模試を受け、模試の後は浮き彫りになった弱点分野を基礎から復習するなど、とにかく勉強漬けの毎日でした。
山野さん:僕は高校の先生から、「夏は毎日、学年の数字プラス4時間は勉強しよう」と言われていました。つまり、高1は5時間、高2は6時間、高3は7時間です。そのアドバイスに素直に従い、高3のときは駿台の自習室に朝9時に行って、休憩を挟みながら21時まで勉強していました。
ただ、現役時代の夏休みの最大の失敗は、基礎が固まっていないのに過去問を解き始めたことです。過去問は基礎学力が大前提で、それがないのに手を出してもまったく力がつかず、時間だけを無駄にしてしまうことになるので、これは大きな反省点でしたね。
--夏休み中に東大模試があるのでつい不安になりますが、過去問については「焦りは禁物」ということですね。
原田さん:はい。私もその点は山野さんに共感します。先ほど夏から過去問を始めたと言いましたが、苦手な数学や、まだ勉強が足りていなかった古文や漢文、地理については、基礎力が十分ではなかったこともあり、特に数学は過去問に着手したのが共通テストの終わった後でした。夏休みの段階では比較的順調だった英語や世界史から始めたのですが、復習では教科書に立ち戻ることも多く、得意・不得意に関わらず、基礎をしっかり固めることが最優先だと私も思います。
その点、駿台のテキストは薄くて問題数は少ないのですが本質をとらえていて、それを何度も丁寧に復習することで重要なポイントが自然と身に付いていくんです。
山野さん:駿台の授業は基礎の根本的な理解を重要視されていますよね。基礎的な良問を1問ずつ掘り下げてじっくり解説してもらえるので、先生の板書と口頭設問で大事なポイントをおさえることができます。東大の入試は奇問難問の類ではなく、基礎の組み合わせだと思うので、こうした駿台での授業がとても役に立ちました。単に公式を暗記するのではなく、基礎を抑えながら現象を読み解くので、初見の問題でも解き方が見えてくるようになるんです。
だからこそ浪人のときは、「まずは基礎を盤石にして、過去問はその後に挑もう」と決め、僕も原田さんと同じく、とにかく駿台のテキストの復習を徹底的にやりました。一方で、「家に帰ってからは一切勉強しない」というルールをつくってメリハリをつけ、駿台にいる時間は集中して取り組めるよう自分を追い込みました。
--東大を目指すうえで、いちばん大変だったこととそれを乗り越えたきっかけを教えてください。
原田さん:東大向けの数学が直前まで伸びなかったことです。高3の秋に受けた2回目の東大模試でも、数学の偏差値は30-40台。さすがに焦りましたが、とにかく駿台の予習復習をメインにし、授業の後には先生の講義や板書を思い出しながらテキストの復習を愚直に続けました。すぐに成果は現れなかったものの、そのテキストに東大の数学に必要なエッセンスが凝縮されていたのか、本番の入試では合格者平均より高い点数を取ることができました。
山野さん:僕の場合は、現役時代も浪人時代も、モチベーションの維持に苦労しました。現役時代は模試で東大の判定が悪く、「東大を諦めて志望校を下げる」というマイナス思考に引っ張られそうになりました。ただ、「目標を下げたら自分の実力も下振れしてしまう」と思い、共通テスト本番で大失敗して足切りギリギリでも、モチベーションを奮い立たせて東大志望を貫きました。
一方で浪人のときは、現役時代の貯金があった分早々にA判定が出ていたのですが、今度は「A判定だから少しくらいサボって良い」という、別の意味でのマイナス思考に流されないように気をつけました。同じA判定が出ている友達と「勉強しなかったら落ちるぞ」と励まし合って、モチベーションを上げました。

「東大は最高に楽しい」今は辛くてもあきらめないで
--保護者の方からはどんなサポートがありましたか。
山野さん:両親は、小さいころから基本的に僕が「やりたい」と言ったことは自由にやらせてくれました。大学選びもすべて僕に一任してくれ、現役時代は共通テストで足切りギリギリでの出願で、合格が厳しいにも関わらず、両親は特に何も言いませんでした。普段の生活では、自習の後、僕が疲れていると駅まで迎えてに来てくれたり、浪人時代も毎日お弁当を作ってくれたり、感謝することばかりです。
原田さん:私の両親は私に浪人してほしくなかったようで、模試でA判定が出ていても、「本当に東大を受けるの?」と半信半疑でした。両親にとって東大は雲の上の存在で、自分の娘が合格するなんて想像すらできず、不安でしかなかったのでしょう。それが少し辛く感じることもありましたが、共通テストと2次試験の当日には手書きのメッセージを持たせてくれ、それを読んで試験場で気持ちをリセットすることができました。合格発表のときは両親共とても喜んでくれて、すごく嬉しかったです。
--おふたりはこの4月に東大に入学したばかりですが、学校生活はいかがですか。
山野さん:毎日、本当に楽しいです。僕は理二ですが理一や理三も混合のクラスで、理三のクラスメイトには頭の回転が速すぎてびっくりさせられることもあります(笑)。バスケとサッカーのサークルに入り、自分とは異なる環境・文化で育った友達と話すことがすごく新鮮です。
原田さん:私がいる文三は女子の割合が約4割で、東大の中では女子がとても多い環境です。すでに出会えてよかったと思える友達がたくさんでき、勉強だけでなく多様な方面に好奇心がある人が多くて、いろいろなことを教わっています。私自身は幼少期から親しんできた音楽をずっと続けていて、吹奏楽のサークルや、第二外国語のフランス語の勉強も楽しいです。
--東大合格まで多くの苦労を乗り越えてきた甲斐がありましたね。東大だからこそ見える景色を、これからもっとたくさん見ることができるのではないでしょうか。最後におふたりから、東大を目指す受験生に向けて、激励のメッセージをお願いします。
山野さん:高校時代もすごく楽しかったけれど、東大にはユニークで多才な人たちがたくさんいて、良い意味でいろいろな刺激を受けられる最高の環境です。3年からは後期課程が決まりますが、世界最先端とも言える研究の場に身を置けるのは今からとても楽しみです。今、受験勉強が辛くても、その後は最高に充実した時間が待っているので、苦しいときもそれを目標に、ぜひ東大を目指してほしいと思います。
原田さん:私も受勉勉強は辛かったですが、入学した今は、その辛さを肯定できるくらい東大に来て良かったと心から思えます。受験勉強をしている中で、「本当に自分が東大に行けるのかな」と自信をなくすこともあると思いますが、最後まであきらめないで頑張ってください。
--ありがとうございました。

東大合格という同じ目標を達成する、おふたりの過程のお話が興味深かった。幼少期から勉強習慣作り、友人との交流を大切にしつつ、スポーツなど好きなことに没頭する経験などを礎に、公立中高に通いながらそれぞれのやり方で努力を重ねた結果が見事に結実したストーリーは、これから東大を目指す受験生と保護者の皆さんにも、大いに参考になるのではないだろうか。
駿台の東大情報ポータルはこちら駿台の講習で東大対策