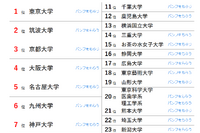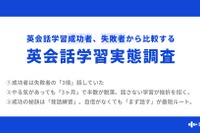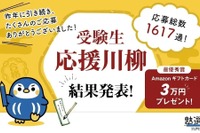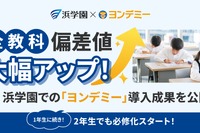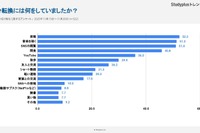関西を中心に約150教室を運営する総合教育機関の成基は、生成AIを活用した不登校支援の研究結果を2025年3月23日に東京で開催された「AI時代の教育学会」で発表した。
成基が運営するオンラインフリースクール「シンガク」では、村上実優教室長の情報をプロンプトに登録した「AIの村上先生」を活用し、子供たちに一定期間使用してもらった。その後、生成AIに対するイメージの変化や「AIの村上先生」と「リアルな村上先生」との比較を調査した。結果として、「生成AI」の効果として「時間の制約がなく利用できる点」や「幅広い情報を提供できる点」があげられた。
一方で、「リアルな村上先生」の利点として、「AIでは再現できない面白さ」や「話を聞いているのが楽しい」「創造性、柔軟性、倫理的判断能力に優れている」などの回答があった。子供たちにとって「生成AI」は学習や情報収集のサポートツールとしての価値を持つが、会話の継続性や対話への意欲には限りが見られた。特に、会話を続けるためには、リアルな村上先生が持つ「人間らしさ」や「面白さ」といった要素が重要であることがわかった。
不登校の子供たちにとって、人との直接的な対話に不安を感じる場合でも、AIなら気軽に相談できるという利点があるが、最終的にはリアルな人との関わりが重要であることが示唆された。生成AIの活用と並行して、子供たちに対するリアルな人の働きかけが重要となることがわかった。
今後は、子供たちが話したいと思えるよう、個々に合わせた「生成AI」のパーソナライズ化や、リアルな先生による「生成AI」の活用方法の紹介や対話練習を検討する必要があると考えられ、継続して研究を続けていく方針である。
生成AIの急速な進化に対し、教育現場でもその活用法には注目が集まっている。文部科学省からも「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」が公表され、教育業界で積極的に取り組むべき課題となっている。成基にとっても、生成AIをどのように活用していくことが有効なのか、その仕組みづくりは重要な経営課題であり、今後も研究を続けていくことで、子供たちが自己理解を深め、心理面およびキャリア面での不安を解消することにつなげていきたいとしている。