
東京ゲームショウ2017が9月21日から24日に幕張メッセで開催される。今回のテーマは「さあ、現実を超えた体験へ」。中学生以下とその家族が入場できるコーナーに、ゲームプログラミングスクールエリアが新設される。

学研ホールディングスのグループ会社、学研プラスは4月2日、人気ゲーム「Minecraft(マインクラフト)」を利用した小中学生向けのプログラミングキャンプを開催する。少人数制のため、パソコンやプログラミング初心者も歓迎している。

ユーバープログラミングスクールは2017年3月、小学生を対象とした無料のプログラミングワークショップを都内の2教室で開催する。太陽系の惑星をテーマにしたオリジナルえほんの企画・開発に参加し、「第5回デジタルえほんアワード」への応募作品の製作にチャレンジする。

アールエスコンポーネンツは2月21日、Raspberry Pi専用のノートPC自作キット「pi-top(パイトップ)」を発売した。プログラミングやコンピューティング、電子機器開発などの学習ソフトがインストールされている。価格は3万6,288円(税別)。

世界各国のプログラミング学習教材に特化したワークショップ&体験型展示会「G7プログラミングラーニングサミット東北」が3月18日、仙台で開催される。今回は次世代のICT人材育成に力をいれる「イトナブ石巻」も参加。入場無料、ワークショップ参加費500円。

LEGO education正規代理店のアフレルは、教育版レゴマインドストームEV3を使った家庭用プログラミング学習教材「ホームスクーリングEV3デスクロボ」の無料体験モニターを募集する。対象は新小学4年生の親子。2月26日までWebサイトにて応募を受け付ける。

ソフトバンクコマース&サービス(ソフトバンクC&S)は、Makeblock社と日本国内での正規販売代理店契約を締結。2月17日より、STEM教育用ロボット「mBot(エムボット)」3種の取扱いを開始する。
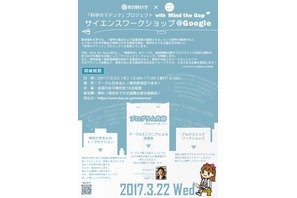
東京理科大学はMind the Gapの協力により、女子高校生を対象としたサイエンスワークショップを3月22日に六本木ヒルズにあるグーグル日本法人で開催する。参加費は無料だが、事前にWebサイトからの申込みが必要。

文部科学省は2月14日、学校教育法施行規則の一部を改正する省令案、ならびに幼稚園教育要領案、小中学校における次期学習指導要領案を公開した。3月15日まで、次期学習指導要領に対するパブリックコメント(パブコメ)を実施している。

中高生向けのプログラミング教育を行うライフイズテックは、感情認識人型ロボット「Pepper(ペッパー)」を活用したプログラミング教育プログラムを開発し、静岡県藤枝市の公立中学校へ提供した。

プログラミングクラブネットワークは2月13日、プログラミング講師のための「PCNオフィシャル講師認定制度」を開始した。認定後は、PCN公認の講師「PCNメンター」として、日本と世界でプログラミング教育活動ができる。

ライフイズテックは、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの協力で3月11、12日、中高生のためのプログラミング教育ワークショップ「VR CAMP with PlayStation VR」を開催する。ゲームを作り、バーチャルリアリティ(VR)システムで実現する楽しさが体験できる。

NTTデータは3月11日・12日、「春のこどもIT体験」をNTTデータ駒場研修センターで開催する。小学生をおもな対象に、保護者同伴で参加できる。参加費は無料。2月19日までWebサイトで申込みを受け付けている。

埼玉大学STEM教育研究センターは3月29日から31日までの2泊3日、浅草の台東区民館で国際STEMキャンプ「STEM Robotics Workshop」を実施する。IoTをテーマに、ロボット作りとプログラミングに挑戦する。定員は先着15人。

埼玉県戸田市は2月9日、2020年から小学校で必修化されるプログラミング教育に関する教員研修の実施にあたり、インテルと協働して取り組む覚書の調印式を行った。インテルと自治体がこのような覚書を締結するのは、埼玉県では初めてだという。
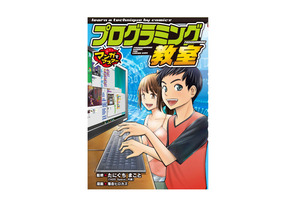
小学校でのプログラミング教育必修化が文部科学省で検討され、子ども向けのプログラミング教室やワークショップなどが人気を博すなど、プログラミング教育に対する関心が高まる中、ポプラ社から「マンガでマスター プログラミング教室」が発売された。